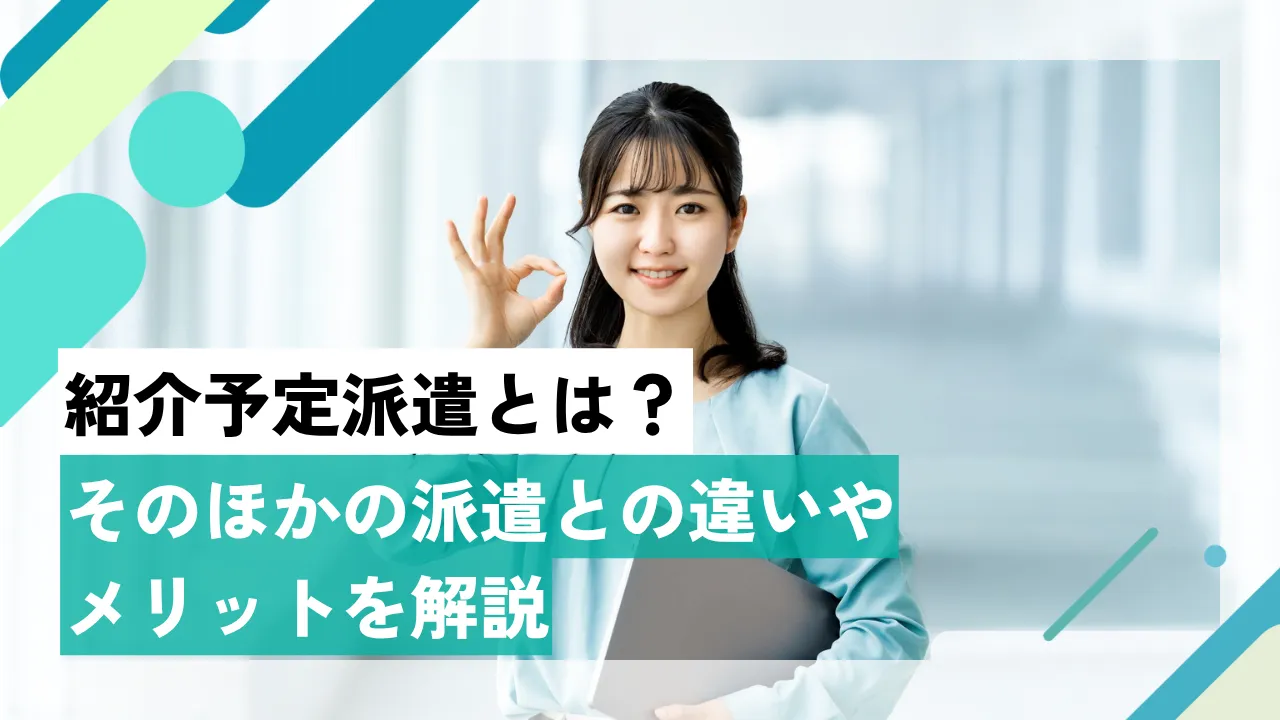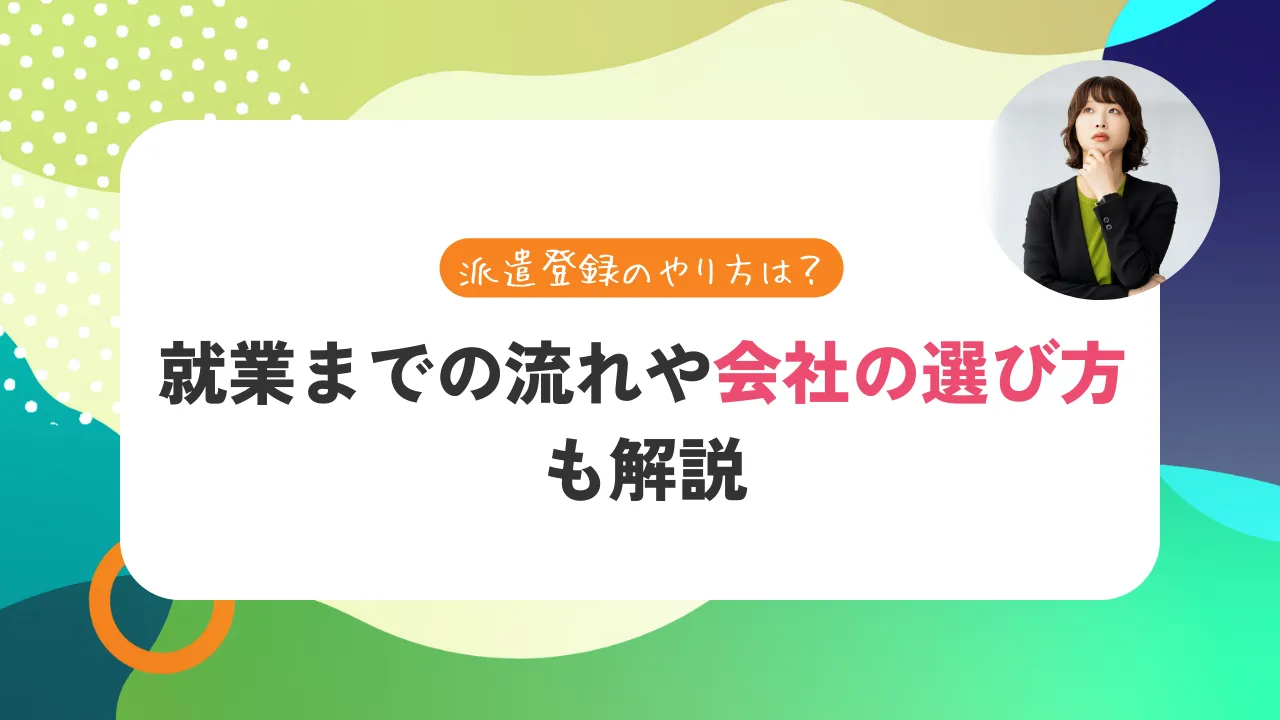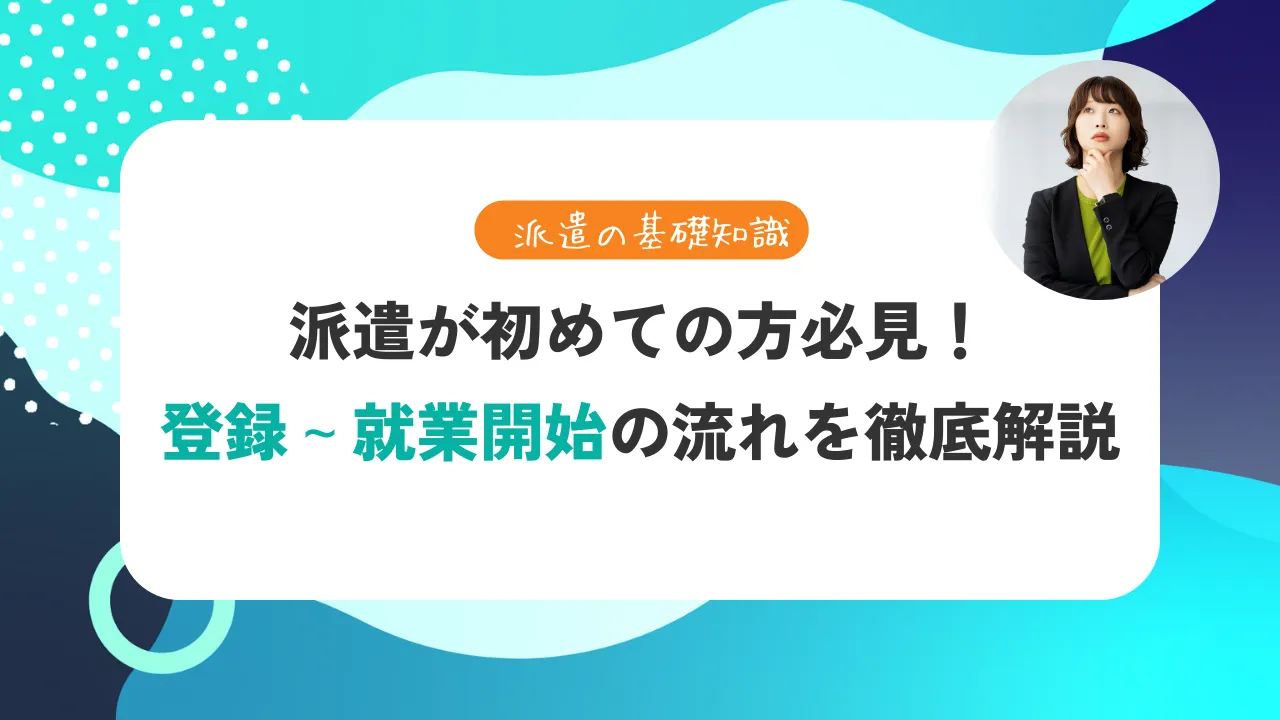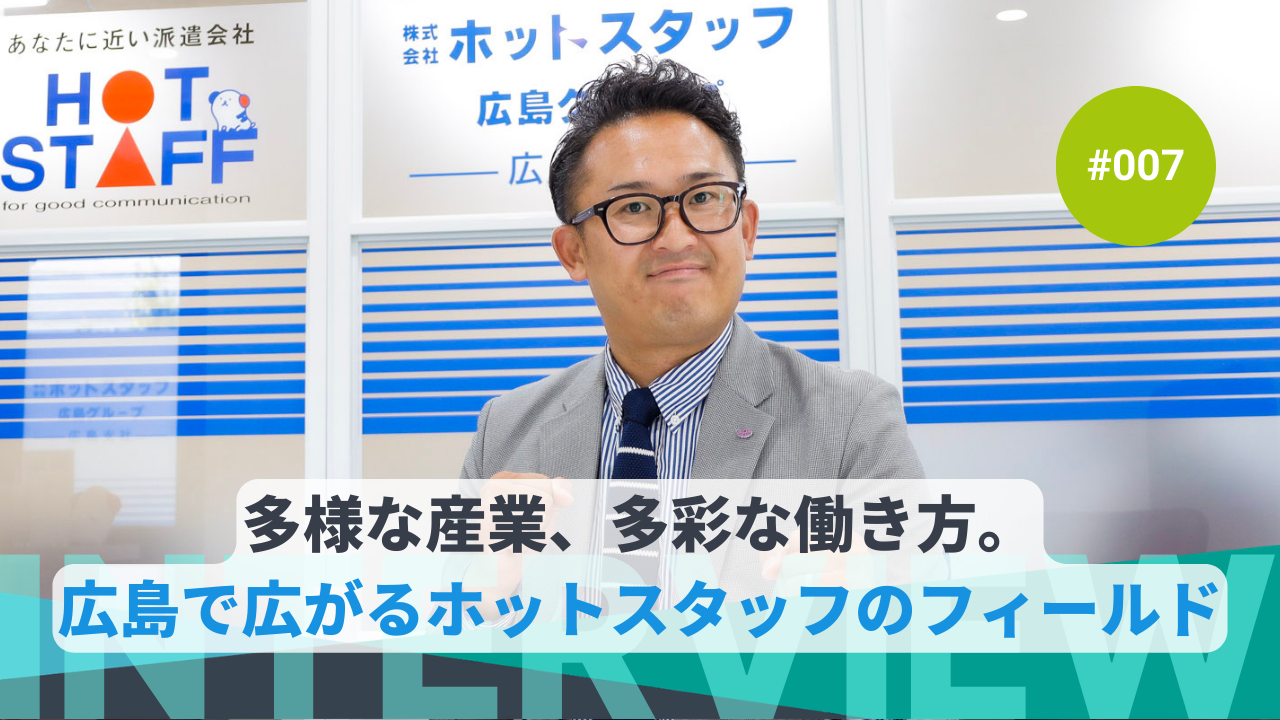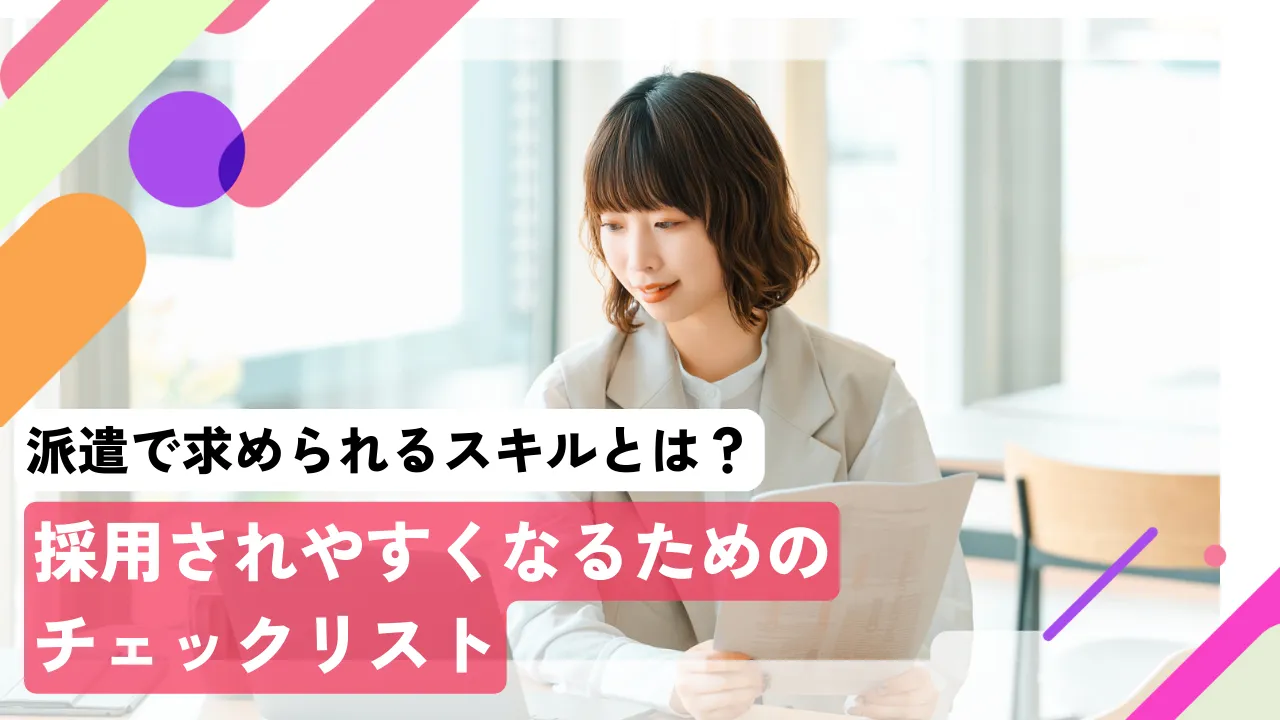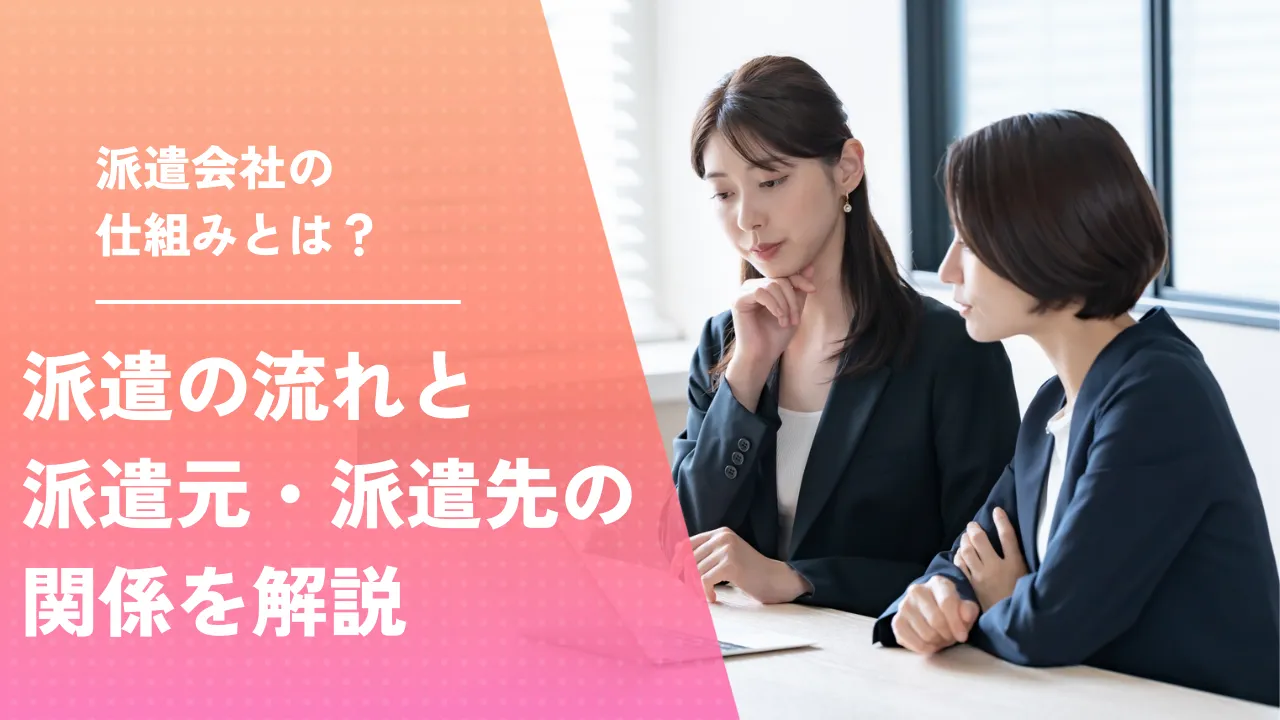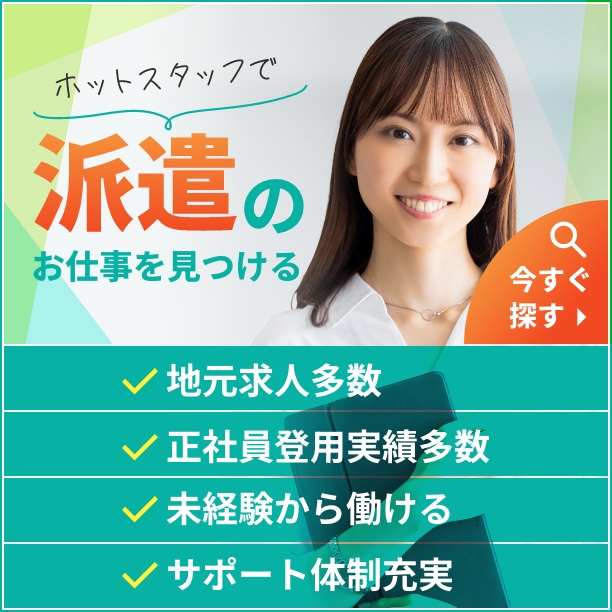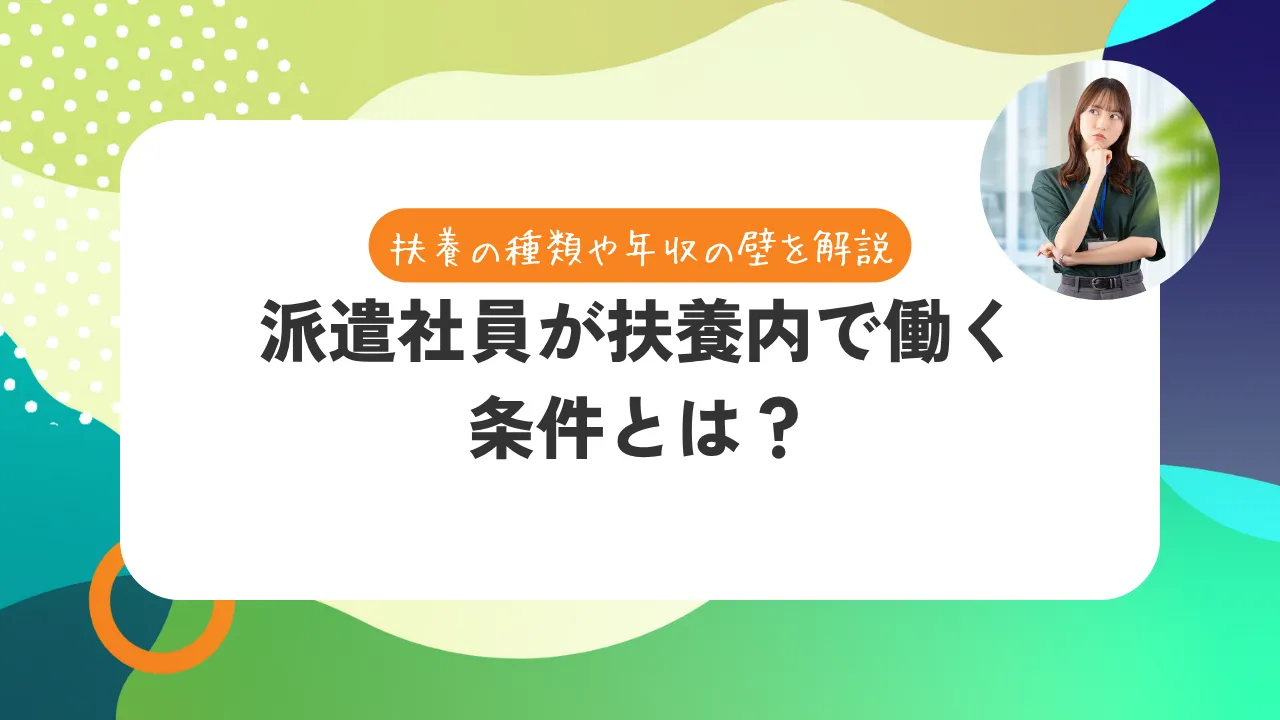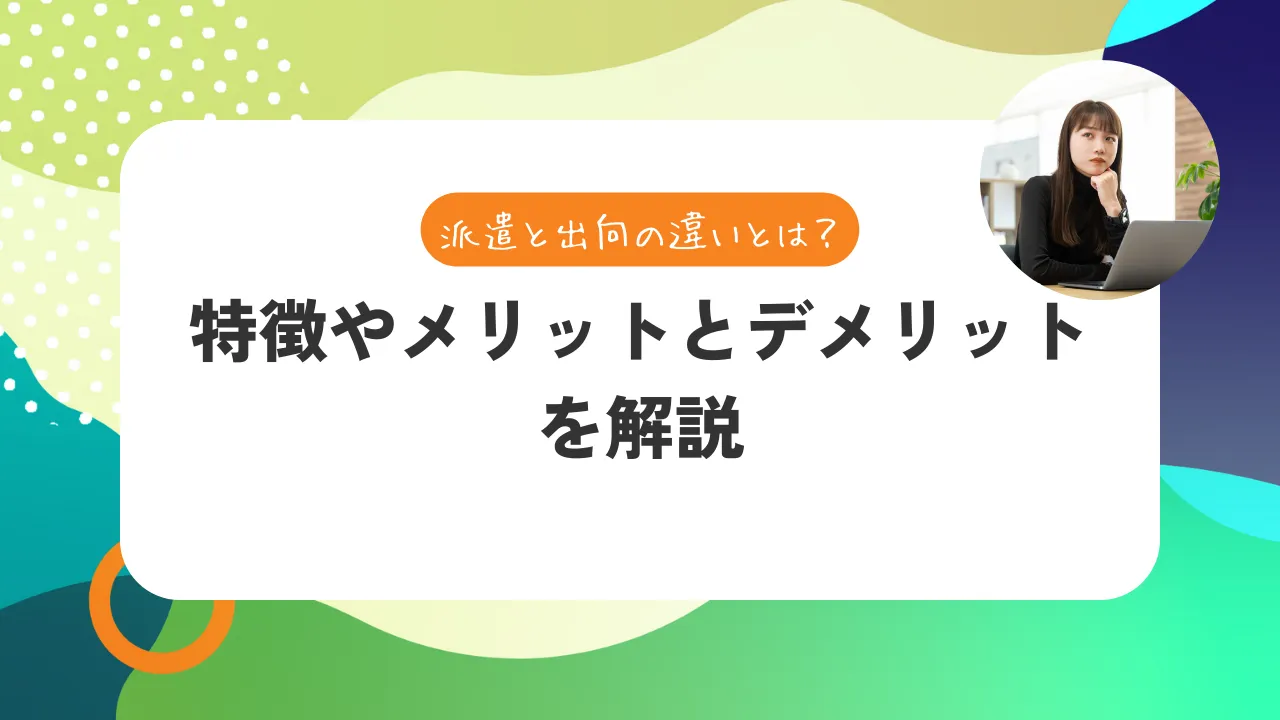派遣という働き方を検討している場合、給与や福利厚生などに関係する“同一労働同一賃金”について把握しておくことが大切です。
とはいえ「この言葉を耳にしたことはあるけれど、どのようなものなのかがわからない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、同一労働同一賃金の概要を、派遣社員にとってのメリット・デメリットとあわせて紹介します。
目次
派遣社員が押さえておきたい同一労働同一賃金とは?

“同一労働同一賃金”とは、正規雇用と非正規雇用とのあいだで生じる、不合理な待遇差の解消を目指すものです。
労働者派遣法の改正により、2020年(令和2年)4月に義務化されました。
現在では、“業務内容や責任の程度が同じであれば、雇用形態に関係なく同等の賃金を支払うべき”という考え方をもとに、各企業で対応が進められています。
この原則が導入された背景には、どのような雇用形態でも待遇に満足して働きつづけられる環境をつくり、多様な働き方を選びやすくすることがあります。
以前は、同じ仕事をしていても「雇用形態が違う」という理由で、正規雇用と非正規雇用の待遇に差が生じていました。
給与から各種手当の有無、福利厚生に至るまで、待遇の差が大きいと働く方々のモチベーションが低下し、業務の生産性や意欲にも影響を与えかねません。
時代とともに労働の多様化が進み、派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用で働く方が増加したことを受け、不合理な待遇差をなくす制度の導入が求められたのです。
近年は、多くの企業で労働環境の整備が進められているため、派遣社員であっても公平な条件で業務に取り組めるでしょう。
ただし同一労働同一賃金において、正規雇用と非正規雇用のあいだで待遇差が生じていたとしても、問題とならない場合もあります。
たとえば、派遣先企業で働くフルタイムの正社員に対しては食事手当が支給され、労働時間が6時間以下の派遣社員には派遣元から食事手当が支給されないといったケースです。
このような待遇差は合理的と判断され、派遣元も同一労働同一賃金の義務を果たしているとみなされます。
参照元:厚生労働省「派遣労働者の ≪同一労働同一賃金≫ の概要 p2」
同一労働同一賃金における派遣社員の待遇を決める方式

同一労働同一賃金を実現するために派遣社員の待遇を見直すのは、雇用主にあたる派遣元です。
待遇の決定に際して派遣元は、“派遣先均等・均衡方式”もしくは“労使協定方式”のいずれかを選択し、派遣社員の基本給や賞与などを定めます。
では、具体的にこの2つの方式がどのようなものなのかを以下で見ていきましょう。
派遣先均等・均衡方式
“派遣先均等・均衡方式”とは、派遣社員の待遇を、派遣先企業で同一の仕事をしている正社員と同等にする方式です。
基本給から賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練、安全管理に至るまで、すべての待遇を派遣先企業の正社員と同等に設定し、同一労働同一賃金に対応します。
派遣社員にとって同等の待遇は大きなメリットとなるうえ、快適に働ける要素にもなるでしょう。
しかし、派遣先企業の待遇が直接反映されることが、デメリットとなる可能性もあります。
「平均よりも基本給が低い」「福利厚生が充実していない」など、派遣先企業の待遇がほかの企業よりも良くない場合は、待遇差がなくとも不満が募りかねません。
派遣元が派遣先均等・均衡方式を選択している場合は、派遣先企業の待遇についての説明を受け、納得したうえで働きはじめることが大切です。
労使協定方式
派遣先企業の待遇が直接反映される派遣先均等・均衡方式に対し、派遣元が派遣社員の待遇を決定するのが“労使協定方式”です。
派遣元と労働組合または派遣元で働く正社員の代表者のあいだで結ばれた労使協定の内容に基づいて、派遣社員の待遇を決定するのが特徴です。
ただし派遣社員の待遇は、自由に決められるわけではなく、合理的な範囲内で決定しなければなりません。
たとえば、派遣社員の給与は、厚生労働省が公表する職種や地域別の賃金統計データを参考に、同一の業務を行う正社員と同等以上に設定する必要があります。
また労使協定方式の利点は、派遣先企業が変わっても待遇は変わらないので、「給与が下がった」「以前提供されていた福利厚生がない」といった影響を受けずに働けることです。
一方、派遣先企業の待遇と同等ではないため、「仕事や責任の程度は同じなのに、正社員と給与や福利厚生に差がある」と感じることもありえます。
収入は安定するものの、待遇は派遣先企業の正社員とまったく同じではないと覚えておきましょう。
同一労働同一賃金の対象となる待遇の具体例
同一労働同一賃金は不合理な待遇差を解消するためのものであり、待遇の決め方には2つの方式があるとお伝えしました。
では、格差をなくすべき派遣社員の“待遇”とは、具体的にどのようなものを指しているのでしょうか。
その具体例は、以下の通りです。
【同一労働同一賃金の対象となる待遇の具体例】
- 賃金
- 福利厚生
- 教育訓練
一つずつ確認していきましょう。
賃金
同一労働同一賃金の考え方では、業務内容や責任の程度が同じであれば、派遣先企業の正社員と派遣社員の賃金に不合理な差を設けてはならないとされています。
対象となる賃金には、基本給や賞与、各種手当が該当します。
ただし、正社員と派遣社員の業務内容や責任の程度、勤務日数などが異なり、それをもとに決定した賃金に差が生じているのであれば問題ありません。
たとえば“週に5日8時間勤務の正社員と、週に3日5時間勤務の派遣社員”では労働時間や勤務日数が異なるため、基本給に差があっても合理的とみなされるわけです。
同一労働同一賃金の義務化によって、派遣社員が安心して働ける環境が整いつつあるからこそ、考え方や詳細な情報に対する理解を深めておくことが重要です。
福利厚生
福利厚生も、派遣先企業の正社員と派遣社員とのあいだで不合理な差を設けてはならないとされています。
雇用形態に関係なく、働く全員に提供される福利厚生の例としては、以下のようなものがあります。
【不合理な待遇差が認められていない福利厚生の例】
- 福利厚生施設(社員食堂・休憩室・更衣室など)の利用
- 転勤者用社宅の提供
- 慶弔休暇
- 病気休暇
- 健康診断に伴う勤務免除・有給保障
正社員と同一の仕事をしているのであれば、こうした福利厚生は派遣社員にも提供されるため、安心して働くことができるでしょう。
関連記事:派遣スタッフも福利厚生を受けられる?正社員との違いや種類を解説
教育訓練
派遣先企業で業務に必要なスキルや知識の習得を目指し、正社員に対して教育訓練が実施されている場合は、同一の業務に携わる派遣社員も訓練を受けられます。
具体的に同一労働同一賃金の考え方では、以下のような指針が示されています。
教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。
引用元:厚生労働省「不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)について p12」
このように派遣社員にも、派遣先企業の正社員と同様にスキルアップの機会が与えられるため、キャリア形成に役立つでしょう。
教育訓練の内容は派遣先企業によって異なりますが、ビジネスマナー講座やOAスキル研修、eラーニングなど、業務に直結する訓練が提供されるのが基本です。
同一労働同一賃金で派遣社員が得られるメリット

同一労働同一賃金の義務化により、現在では派遣社員の待遇が改善されつつあります。
こうした同一労働同一賃金の実現がもたらすメリットには、どのようなものが挙げられるのでしょうか。
ここからは、その例として以下の3つを見ていきます。
【同一労働同一賃金で派遣社員が得られるメリット】
- メリット①給与の待遇が良くなる
- メリット②安心してライフスタイルに合った働き方ができる
- メリット③キャリアアップが可能になる
メリット①給与の待遇が良くなる
まずメリットとして挙げられるのが、給与の改善が期待できる点です。
派遣先企業の正社員と業務内容や責任の程度が同じであれば、「派遣社員だから」という理由で給与が低く設定される心配はありません。
また、成果や業績によっては昇給・賞与を受けられる可能性もあるため、仕事に対するモチベーションも高まるでしょう。
特に派遣元が派遣先均等・均衡方式を採用している場合は、派遣先企業の正社員と同等の給与を得られるため、仕事への満足度の向上も見込めます。
メリット②安心してライフスタイルに合った働き方ができる
これまでは不合理な待遇差の影響で、派遣社員をはじめ非正規雇用という選択肢は敬遠されがちでしたが、同一労働同一賃金の導入により、その状況は変わりつつあります。
現在では出産や育児、介護といったライフスタイルの変化に合わせ、派遣という働き方を選びやすくなっています。
「柔軟に働きたい」「プライベートの時間も大切にしたい」など、ワークライフバランスを重視する方にとって、この点は大きなメリットとなるでしょう。
同一労働同一賃金には、不合理な待遇差を改善するだけではなく、自分らしい働き方を後押しする側面もあるといえます。
メリット③キャリアアップが可能になる
同一労働同一賃金の導入により、派遣社員のスキルアップの機会も増えています。
派遣先企業が実施する教育訓練を利用して、業務に必要なスキルや専門的な知識を身につけることで、結果としてキャリアアップのチャンスが広がるでしょう。
スキルが向上すれば取り組める仕事の幅も広がるほか、派遣先企業からの評価が良い場合は、長期的な雇用につながるとも考えられます。
派遣社員として働きながら学びの機会が得られる、そしてご自身のキャリアを築ける点は、同一労働同一賃金がもたらすメリットとなります。
関連記事:派遣社員でもキャリアアップできる?スキルを磨く方法を解説
同一労働同一賃金における派遣社員のデメリット

同一労働同一賃金の導入によって、今までよりも派遣という働き方を選びやすくなっている一方、派遣社員がデメリットを感じることもあります。
具体的なデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
デメリット①良好な人間関係を築けない可能性がある
まず挙げられるのが、派遣社員の待遇の改善によって、派遣先企業の正社員が不平不満を抱く可能性があることです。
これが原因で良好な人間関係を築けず、ひいては就業が困難になるおそれもあります。
正社員が不平不満を抱く理由としては、“同一労働同一賃金の内容を把握できていない”“正規雇用の待遇を悪くする企業も存在する”といった2つが挙げられます。
派遣社員が正社員と同一の仕事をしていることを、正社員が把握できていない場合「派遣社員は楽な仕事ばかりしている」と誤解されてしまうかもしれません。
また派遣先企業によっては、非正規雇用の待遇を良くするのではなく、正規雇用の待遇を悪くして、同一労働同一賃金に対応するケースもみられます。
給与を下げたり、賞与をなくしたりと、正社員にとってデメリットの大きい対応が不満につながるわけです。
こうした理由で、正社員からネガティブな印象を持たれ、良好な関係を構築するのが困難になる可能性があります。
関連記事:派遣先で生じる人間関係の悩みとは?対処するポイントを解説
デメリット②雇用されにくくなる場合がある
同一労働同一賃金の導入により、派遣社員として働けるチャンスが減るおそれがあります。
派遣社員の待遇の改善に伴って、派遣先企業のコストが増加するためです。
派遣サービスの利用に際しては、派遣先企業が派遣元に“派遣料金”を支払う仕組みとなっており、この料金には派遣社員の給与や社会保険料なども含まれています。
派遣社員の給与や福利厚生費が上がると、派遣先企業は派遣元に対して、今までよりも多くの派遣料金を支払わなければなりません。
派遣社員の割合が多い企業の場合は、支払い額の増加により経営状況が悪化するリスクも出てきます。
こうしたリスクを回避するため、派遣社員の受け入れを縮小する可能性があるわけです。
待遇に疑問を感じたときに派遣社員ができること
派遣社員として働きはじめる際には、賃金や福利厚生に関する疑問を解消しておくことが不可欠です。
もし待遇面での疑問が生じた場合は、派遣元に相談してください。
派遣社員には待遇に関する説明を受ける権利があり、派遣元には説明を求められた際、それに応じる義務があります。
派遣元の説明に納得できない場合は、労働基準監督署や都道府県の労働センターなどに相談することをおすすめします。
疑問を抱えたまま放置すると、後々大きな問題に発展する可能性もあるため、早めに解消し、晴れやかな気持ちで仕事を開始しましょう。
同一労働同一賃金は、派遣先企業の正社員と派遣社員の待遇差をなくすための原則
同一労働同一賃金とは、正規雇用と非正規雇用とのあいだで生じる不合理な待遇差の解消を目指すものです。
2020年(令和2年)4月に労働者派遣法が改正され、派遣社員を含む非正規労働者に対しても同一労働同一賃金の適用が義務化されました。
給与から福利厚生、教育訓練に至るまで、派遣先企業の正社員と同等の待遇を受けられるようになり、現在は派遣という働き方を選びやすくなっています。
待遇差の改善を受け、「派遣社員として新たな一歩を踏み出したい」とお考えの方は、ホットスタッフにぜひご相談ください。
派遣という働き方が初めてでも安心していただけるよう、充実した福利厚生をはじめ、きめの細かいサポートを提供いたします。