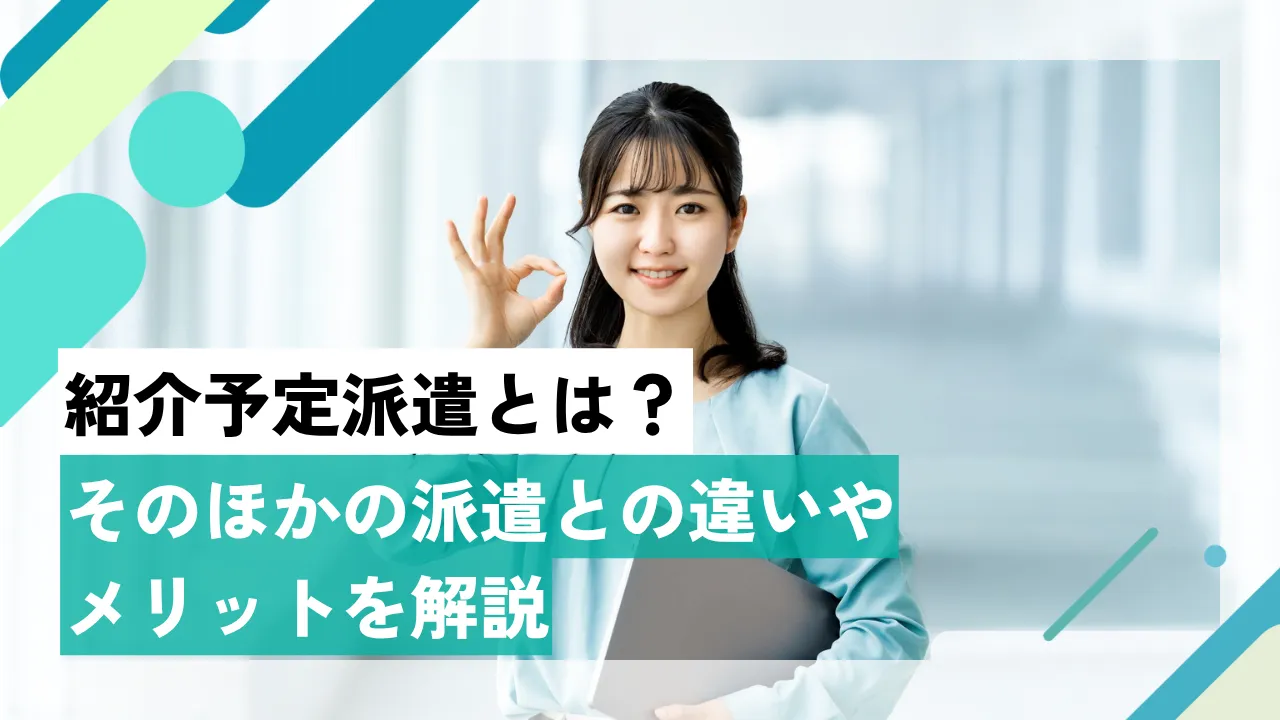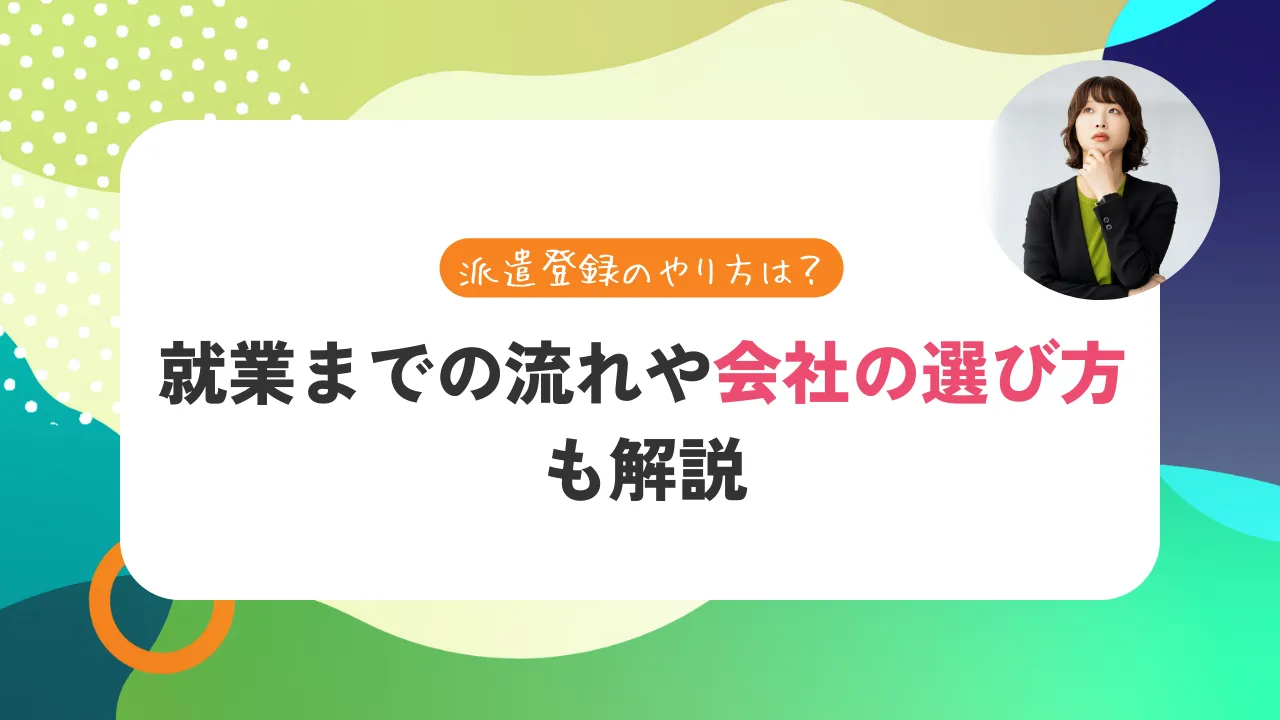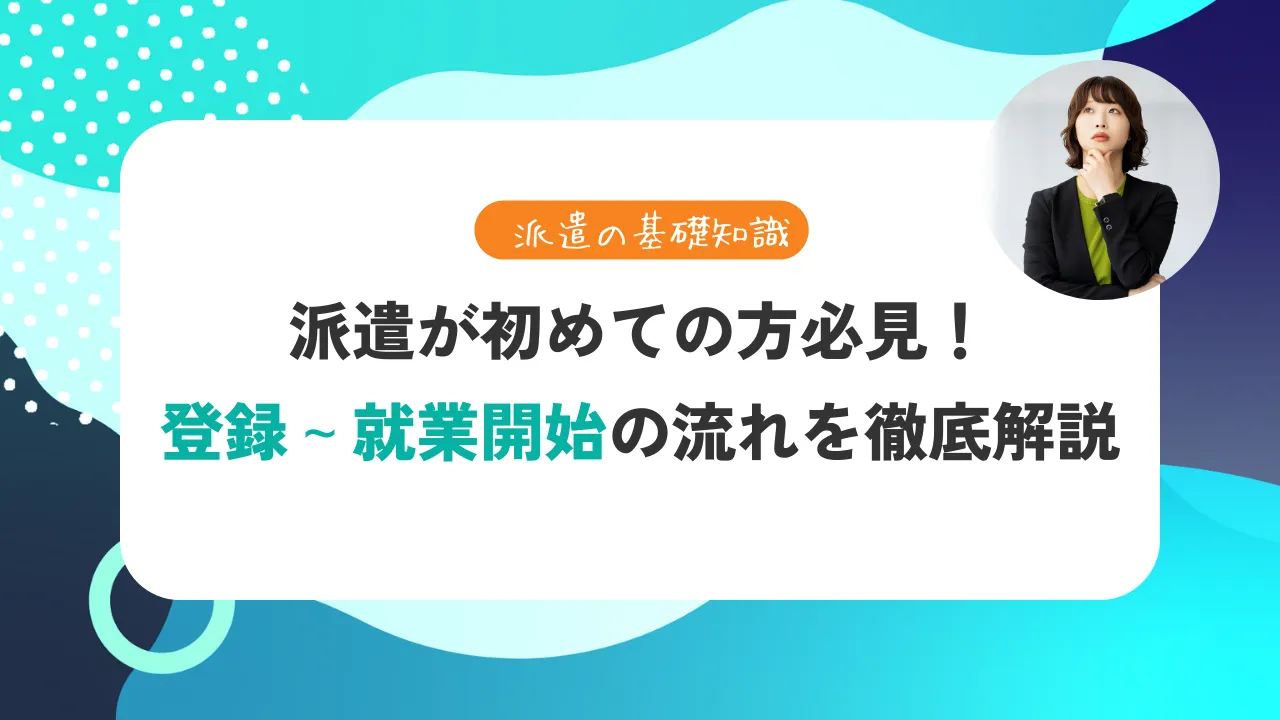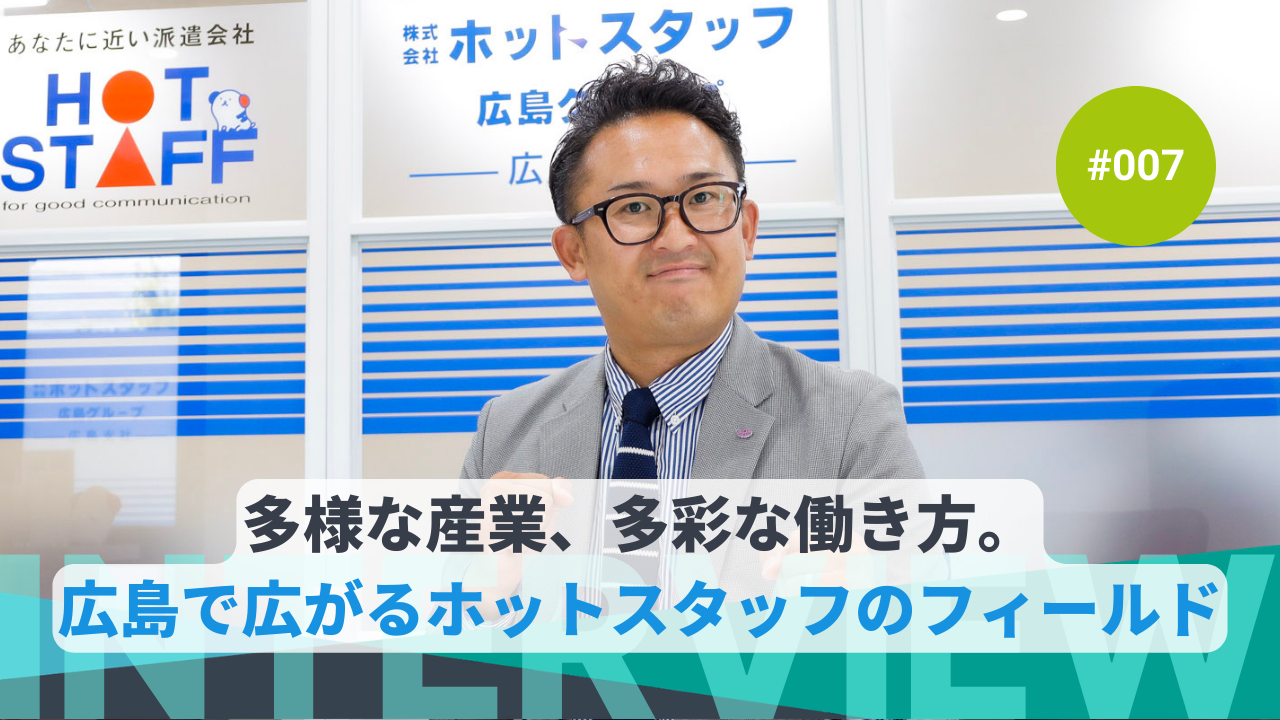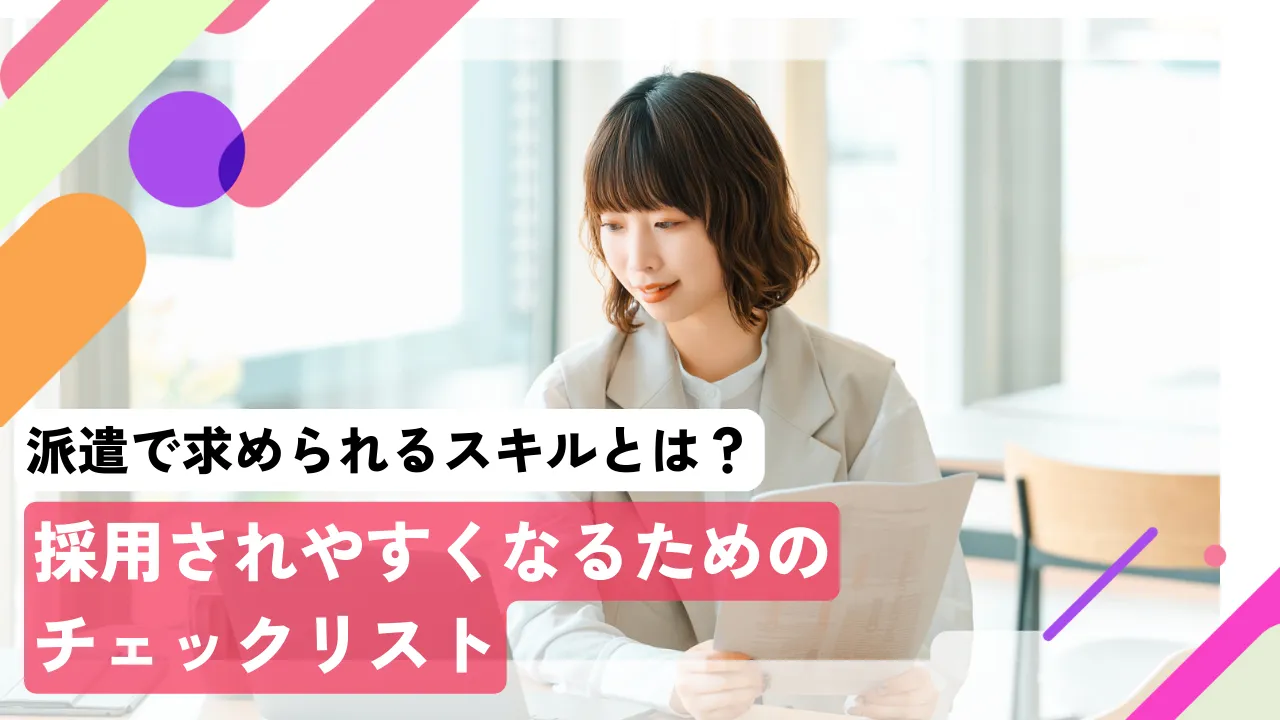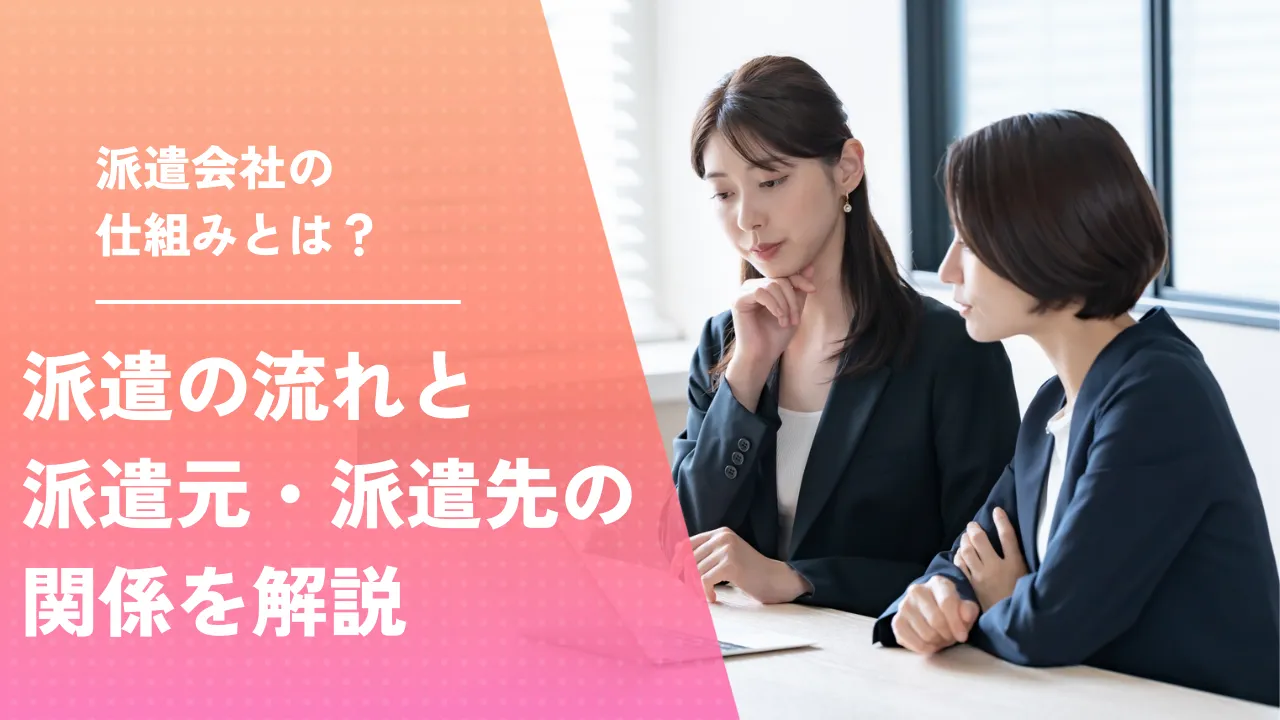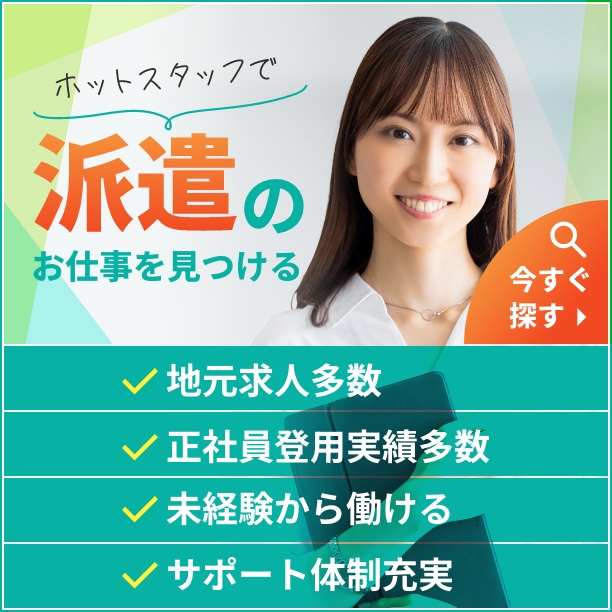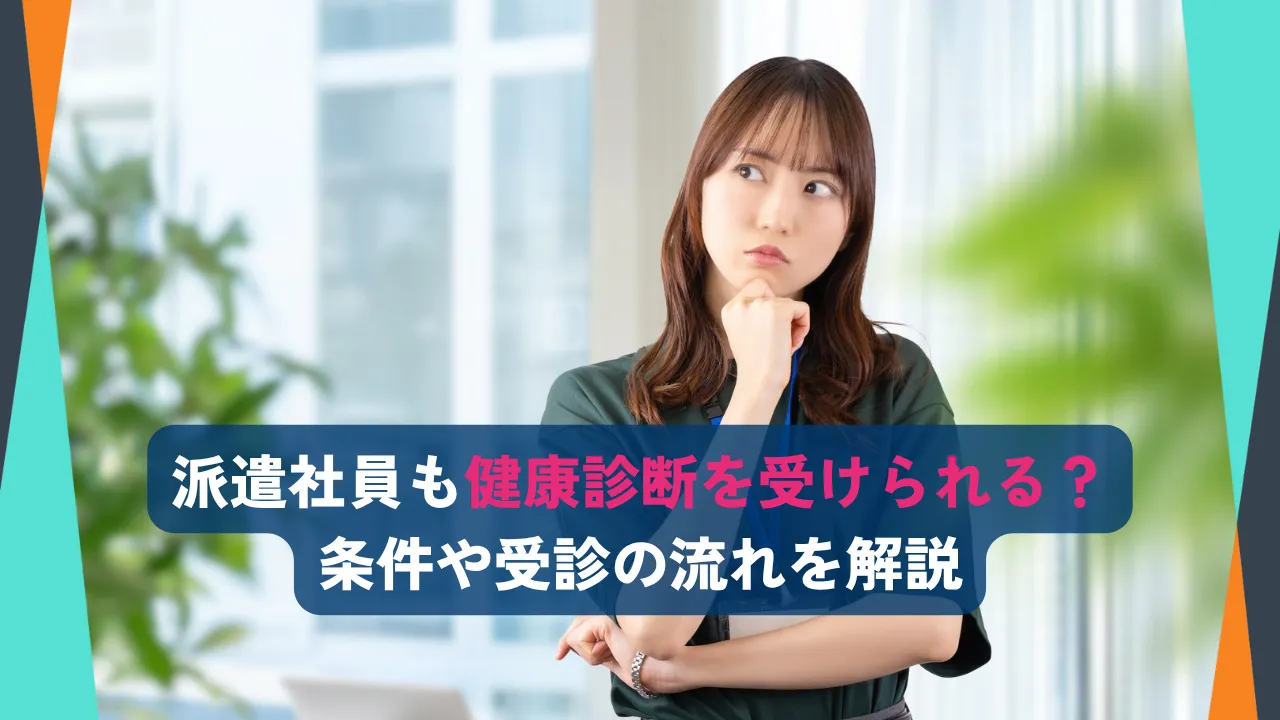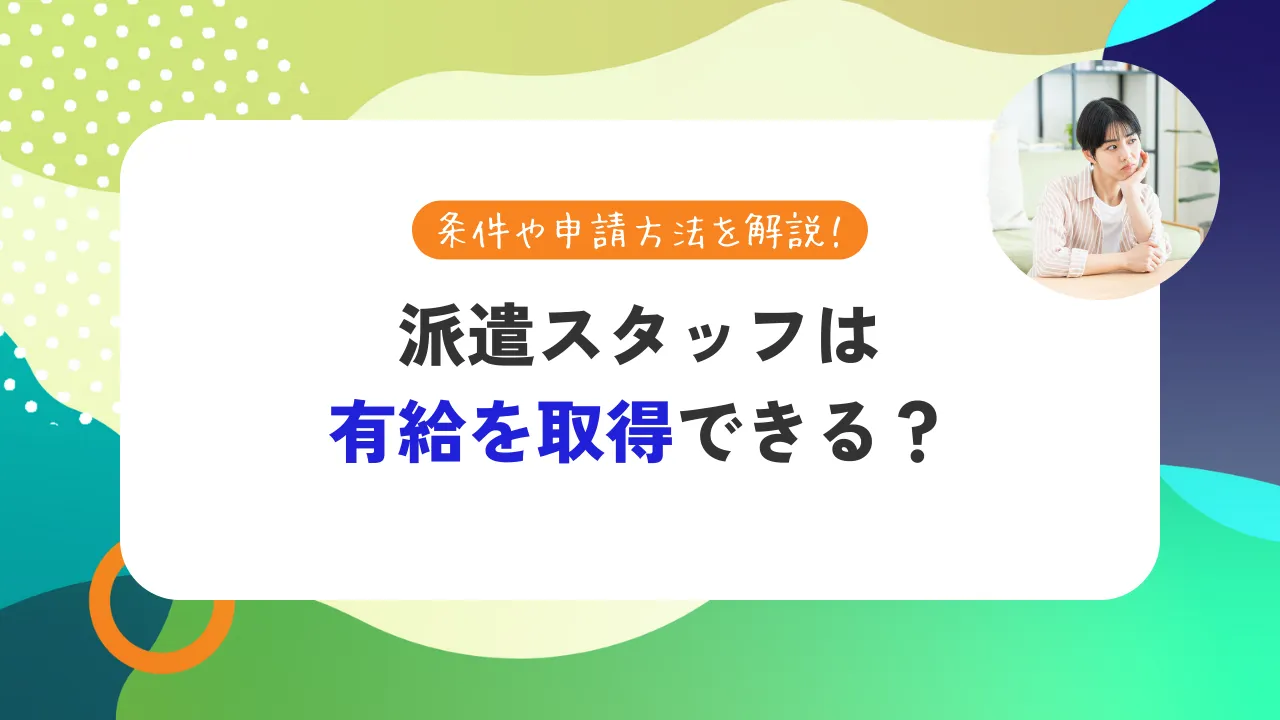派遣社員を目指す方のなかには、「派遣社員は厚生年金に加入できない」と誤解している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし厚生年金は、条件を満たせば雇用形態に関係なく加入できます。
この記事では、派遣社員が厚生年金に加入するための条件を解説します。
充実した福利厚生と最適な働き方が叶う派遣会社を選ぶ際の、参考にしてください。
目次
厚生年金とは

加入条件をお伝えする前に、厚生年金の仕組みについて整理しておきましょう。
厚生年金とは、会社員や公務員など、雇用されて働く方が加入する公的年金制度の一つです。
日本の公的年金制度は、以下のように“2階建て”と表現されます。
【日本の公的年金の仕組み】
| 階層 | 種類 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 1階部分 | 国民年金(基礎年金) | 20歳以上60歳未満の全国民 |
| 2階部分 | 厚生年金 | 70歳未満の会社員や公務員 |
厚生年金に加入し、受給資格を満たしている場合は、原則65歳から国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。
また、病気や怪我で働けなくなったときに受け取れる“障害厚生年金”や、加入者が亡くなったときに家族が受け取れる“遺族厚生年金”の給付も対象です。
ただし、これらを受け取るには、それぞれの受給要件を満たす必要があります。
国民年金との違い
厚生年金と国民年金には、加入対象者のほかにも以下のような違いがあります。
【厚生年金と国民年金の違い】
| 厚生年金 | 国民年金 | |
|---|---|---|
| 保険料の納付額 | 収入に応じて変動 | 定額 |
| 保険料の負担 | 事業主と従業員で折半 | 全額自己負担 |
| 年金の受給額 | 保険料の納付額と加入期間に応じて算定 | 保険料を納付した月数に応じて算定 |
| 受給開始年齢 | 原則65歳(繰り上げ・繰り下げ受給は可能) | 原則65歳(繰り上げ・繰り下げ受給は可能) |
厚生年金と国民年金の大きな違いは、“保険料の納付額”と“保険料の負担”です。
厚生年金の場合は、収入に応じて納付額が変動するため、収入が高いほど手取り額は減ってしまいます。
また、保険料の支払いは、事業主と折半して納付する“労使折半”が一般的です。
一方、国民年金の場合は納付額が定額であり、保険料は全額自己負担となります。
なお、年金の受給開始はどちらも65歳が基準となっており、受給要件を満たせば繰り上げ受給、または繰り下げ受給が可能です。
派遣社員でも厚生年金に加入できる?

派遣社員であっても、雇用条件や労働時間などの条件を満たせば厚生年金に加入できます。
ただし、これには派遣社員だけでなく、厚生年金の加入元となる派遣会社も加入条件を満たしている必要があります。
派遣社員と派遣会社、それぞれの加入条件を次項で詳しく見ていきましょう。
関連記事:派遣社員でも産休や育休は取得できる?条件や手当も解説
派遣社員が厚生年金に加入できる条件
では、派遣社員が厚生年金に加入するには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。
ここからは、厚生年金に加入するための条件を、派遣社員と派遣会社それぞれの視点から説明します。
派遣社員側の条件
派遣社員が厚生年金に加入するには、以下のいずれの条件も満たす必要があります。
【派遣社員が厚生年金に加入するための条件】
- 厚生年金に加入している派遣会社に勤務している70歳未満の方
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、派遣会社で働く正社員やフルタイム従業員の4分の3以上である方
上記の条件を満たす派遣社員は、国籍や性別、また年金受給の有無にかかわらず、厚生年金の加入対象になります。
ただし、労働時間や労働日数が、派遣会社で働く正社員やフルタイム従業員の4分の3に満たない場合でも、以下のすべての条件をクリアすれば厚生年金への加入が可能です。
【厚生年金の加入条件である所定労働時間・日数に満たない場合の例外】
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上である
- 非学生である
- 雇用期間が2か月を超える、または超える見込みがある
- 派遣会社の従業員数が51人以上、または国・地方公共団体に属する派遣会社に所属している
一方、厚生年金保険法では、雇用期間が2か月を超える見込みがなく、契約更新がない場合は、厚生年金の加入適用外と定められています。
そのため、雇用期間が2か月以内の短期派遣では、厚生年金に加入できません。
派遣社員として厚生年金への加入を希望するのであれば、2か月を超えて働くことが不可欠です。
【参照元】
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
派遣会社側の条件
派遣社員が厚生年金に加入するには、雇用主となる派遣会社が厚生年金の適用対象である必要があります。
厚生年金の適用対象となる企業は、以下の4つの種類に分けられます。
【厚生年金の適用対象となる企業の種類】
- 強制適用事業所
- 任意適用事業所
- 特定適用事業所
- 任意特定適用事業所
種類ごとの適用条件を、一つずつ見ていきましょう。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思にかかわらず、厚生年金への加入が義務づけられている企業や組織のことです。
正社員やフルタイムで働く従業員を雇用する法人事業所や国・地方公共団体、また常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所が対象となります。
また、強制適用事業所となる法人は、“株式会社・有限会社・合同会社”といった、すべてが対象です。
ただし、個人事業所の場合は対象外となるケースもあり、理容業や飲食店などの一部のサービス業と農林水産業を営む事業所がこれに該当します。
なお、強制適用事業所が厚生年金への加入手続きを行わない場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に科される可能性があります。
任意適用事業所
任意適用事業所は、法律上厚生年金保険や健康保険といった社会保険に加入する必要はないものの、任意で加入できる企業や組織です。
強制適用事業所に該当しない場合でも、従業員の半数以上から厚生年金保険加入の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ければ、任意で厚生年金に加入できます。
厚生年金の適用事業所でない派遣会社に所属した場合でも、社会保険に加入したい派遣社員が大勢いれば、派遣会社に社会保険への加入を交渉できるかもしれません。
特定適用事業所
1年のうち6か月以上、厚生年金に加入している従業員の総数が51人以上となることが見込まれる事業所を、特定適用事業所といいます。
厚生年金に加入している従業員数は、法人の場合、法人番号が同一の支店や店舗なども含めた全従業員の総数を算出します。
また、個人事業所の場合、厚生年金に加入している従業員の数は、個々の事務所や店舗ごとの従業員数です。
なお、特定適用事業所の規模は徐々に拡大されており、令和6年10月からは対象の事業所で働く短時間労働者も、社会保険の加入対象となりました。
これにより、特定適用事業所で働く短時間労働者や派遣社員も、以前より働きやすい環境が整いつつあります。
参照元:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
任意特定適用事業所
厚生年金に加入している従業員の総数が50人以下の事業所であっても、労働組合またはそれに代わる従業員の同意を得ることで、任意特定適用事業所となる場合もあります。
具体的には、以下のいずれかの同意があったときです。
【任意特定適用事業所に必要な同意】
- 当事業所に勤務している同意対象者の過半数で組織される労働組合の同意
- 当事業所に勤務している同意対象者の過半数を代表する従業員の同意
- 当事業所に勤務している同意対象者のうち2分の1以上の同意
ここでいう同意対象者とは、厚生年金の加入者や70歳以上の被用者、短時間労働者のことです。
この方々の同意を得て必要な手続きを行うことで、厚生年金を含む社会保険への加入が可能になります。
厚生年金の加入対象外となる方

以下に該当する場合は、雇用形態に関係なく厚生年金の加入対象にはなりません。
【厚生年金の加入対象外となる方】
- 70歳以上の方
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である方
- 所定内賃金が月額8万8,000円未満である方
- 学生の方
- 雇用期間が2か月を超えない方
- 国・地方公共団体に属さない、従業員数51人未満の企業や組織に勤務している方
厚生年金の加入対象者は、社会保険の適用事業所に勤務している70歳未満の方であるため、これを超えると加入資格を喪失します。
ただし、70歳を超えて企業に雇用されている方は、勤務先の許可を得て“高齢任意加入制度”に加入できます。
高齢任意加入制度は、保険料を納めた期間が10年に満たない方が受給資格を得るための制度です。
通常、年金を受け取るには、公的年金に加入して保険料を納付していた期間が10年以上必要ですが、これに満たなくとも勤務先を通じて年金事務所に申請すれば加入できます。
しかし、厚生年金の保険料は勤務先が半分負担するので、勤務先の同意を得られないときは、保険料は全額自己負担になる点に注意が必要です。
関連記事:派遣社員が社会保険に加入する条件とは?対象者や手続きの流れを解説
厚生年金の加入と扶養内で働くのはどちらが有利か?
「扶養内で働いて手取り額を増やす」「社会保険料を負担しても世帯年収を増やす」このどちらが有利かどうかは、家計の状況によって異なります。
本人が厚生年金に加入すると、毎月収入に応じた保険料の負担が発生し、手取り額が減ります。
一方、配偶者の扶養内で働く場合は、個別に保険料を納付する必要がないため、本人の手取り額が多くなるのは利点です。
さらに、扶養する側も所得税や住民税の控除が受けられます。
しかし、扶養から外れないようにするためには、得られる収入の額が定められており、世帯収入を増やすのは難しいでしょう。
将来受け取れる年金額も、厚生年金に加入する場合と比べて少なくなるデメリットもあります。
ご自分の希望や、ご家族の意向を踏まえたうえで最適な働き方を検討したいところです。
関連記事:派遣社員が扶養内で働く条件とは?扶養の種類や年収の壁を解説
派遣社員が厚生年金に加入するメリット・デメリット
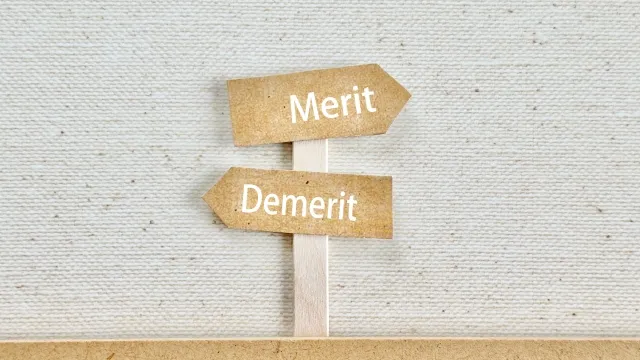
厚生年金への加入は、家計や将来にも大きく影響するため、メリットやデメリットを把握しておくことが大切です。
以下では、派遣社員が厚生年金に加入するメリットとデメリットをそれぞれまとめています。
メリット
派遣社員が厚生年金に加入するメリットは、以下の通りです。
【派遣社員が厚生年金に加入するメリット】
- 将来受け取れる年金額が増える
- 扶養控除が受けられる
- 保険料の支払いは事業主と折半のため、個人の負担が減る
- 障害厚生年金や遺族厚生年金などの保障が受けられる
厚生年金に加入すると、障害厚生年金や遺族厚生年金などの充実した保障が受けられます。
国民年金のみの場合、遺族年金の受給対象は原則として「子のある配偶者」または「子」に限られますが、厚生年金に加入している場合は、子のない配偶者や、一定の条件を満たせば父母、孫、祖父母も対象です。
これ以外にも、病気や怪我で休職したときに傷病手当金を受け取れる制度もあります。
デメリット
派遣社員が厚生年金に加入すると、以下のようなデメリットが生じることもあるので、家計によっては負担となるかもしれません。
【派遣社員が厚生年金に加入するデメリット】
- 給与の手取り額が減る
- 税金の負担が増える
厚生年金に加入すると、収入に応じて毎月保険料が給与から天引きされるため、手取り額は少なくなります。
また、厚生年金の加入条件を満たす収入がある場合は、所得税や住民税といった税金を支払う必要があります。
そのため、「働く時間は増えたけれど、思った以上に手取り額が少ない」と感じる可能性がある点がデメリットです。
派遣社員が扶養内で働くメリット・デメリット
派遣社員が扶養内で働くメリットは、社会保険料の免除や配偶者の所得控除によって収入が増えることです。
一方、デメリットとしては、扶養から外れないために働く時間や収入額を調整しなければならず、世帯収入を増やせない点が挙げられます。
しかし、扶養に入る場合、扶養控除にくわえて配偶者の勤務先企業が“扶養手当”や“家族手当”のような独自の規定を設けているケースがあります。
これは、扶養家族を対象とした手当であり、法律で支給が定められているものではありません。
そのため、規定の有無や支払われる条件、また金額などは配偶者の勤務先企業によって異なります。
ご家族の扶養を希望する場合は登録する派遣会社、ご自分が配偶者の扶養に入る場合は配偶者の勤務先企業で設けられている、扶養手当の規定を確認してみてください。
派遣社員でも労働時間や労働日数などの条件を満たせば、厚生年金に加入できる
派遣社員であっても、労働時間や労働日数などの条件を満たしており、厚生年金の適用事業所となる派遣会社に登録していれば、厚生年金に加入できます。
ただし、学生である場合や、雇用期間が2か月を超えない短期派遣で働く場合は、原則として厚生年金の加入対象にはなりません。
なお、厚生年金に加入できれば、将来受け取れる年金額が増えるだけでなく、障害厚生年金や遺族厚生年金といった手厚い保障も受けられます。
万全なサポートを受けながら派遣として働きたい方は、ホットスタッフにご相談ください。
派遣社員の方とそのご家族お一人おひとりが、潤いある豊かな生活が送れるよう、充実の福利厚生をご提供しております。