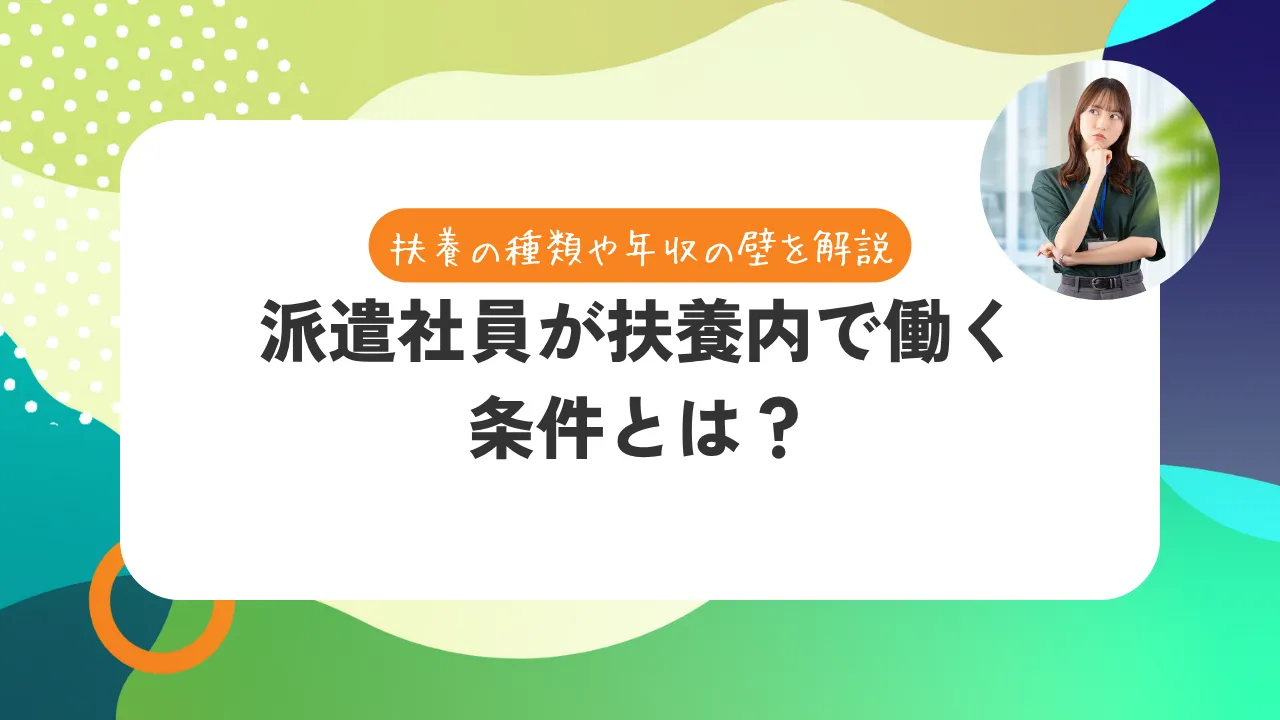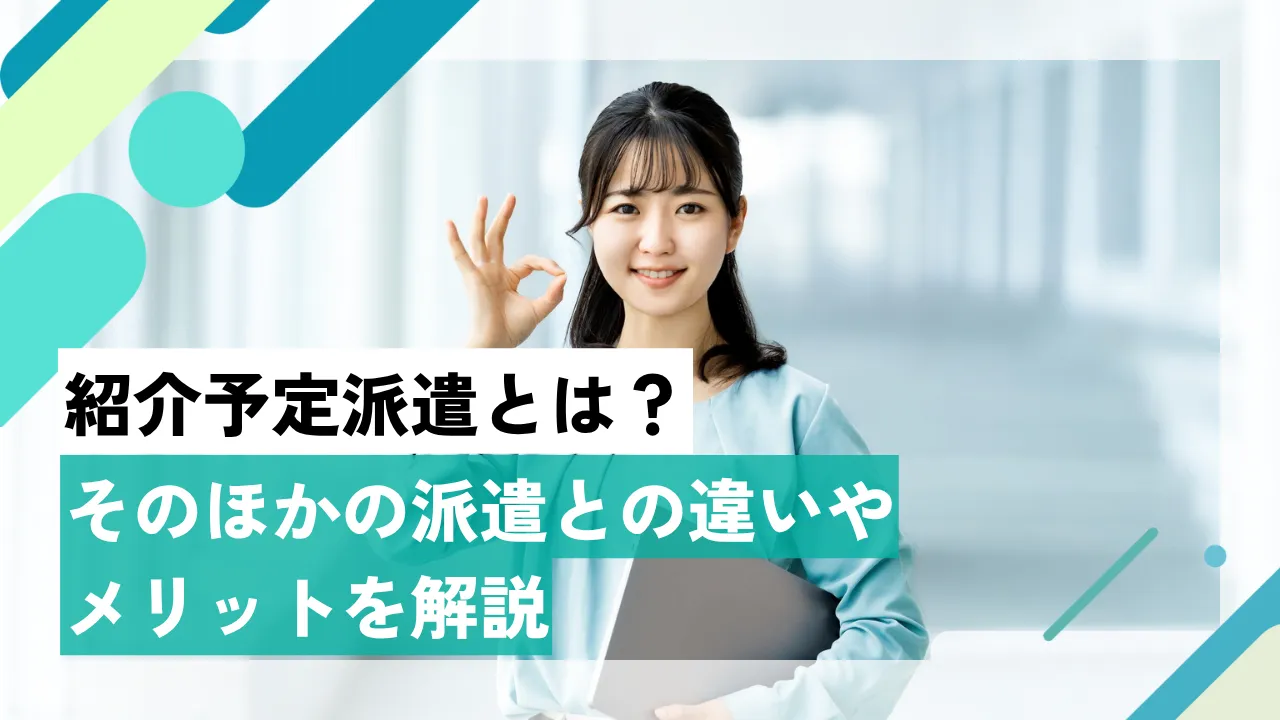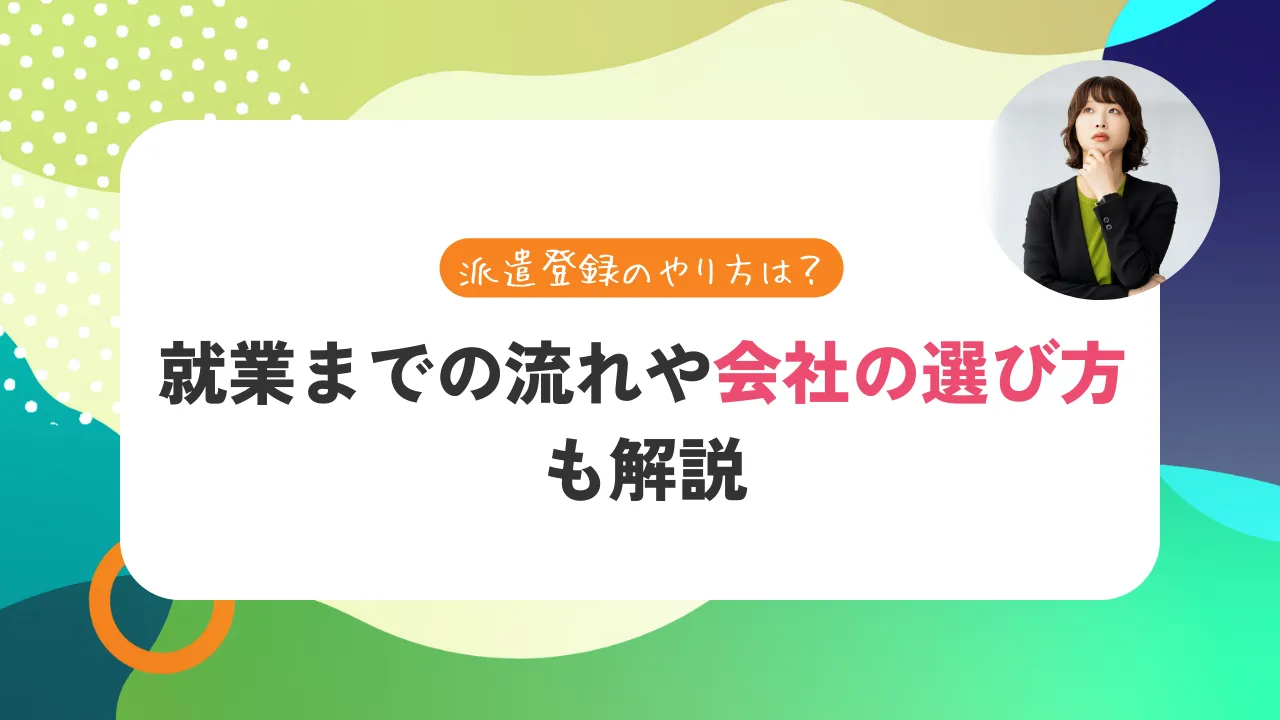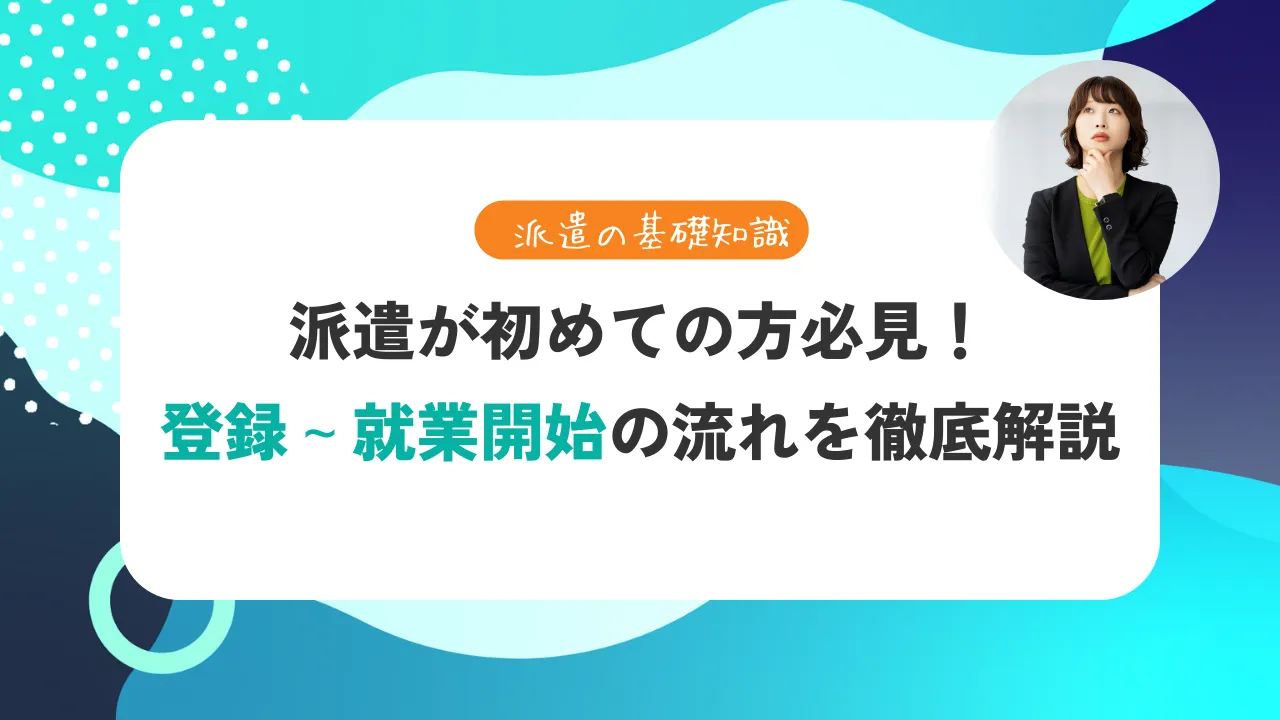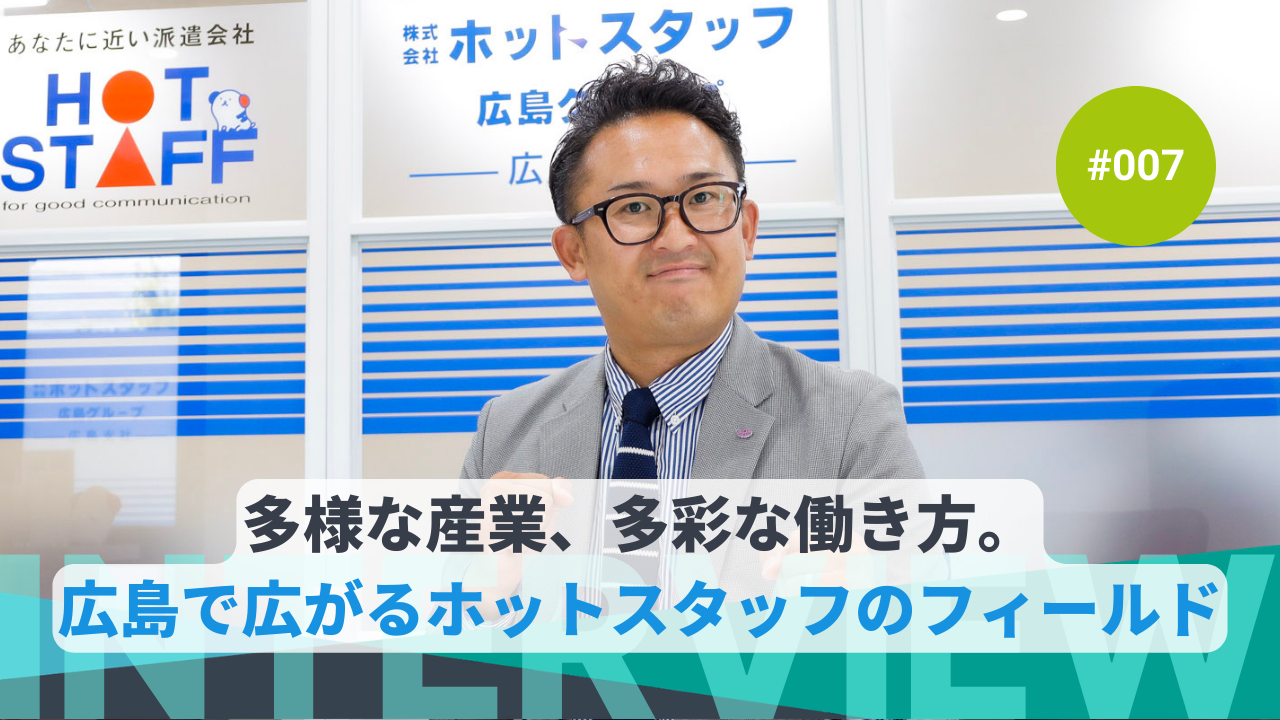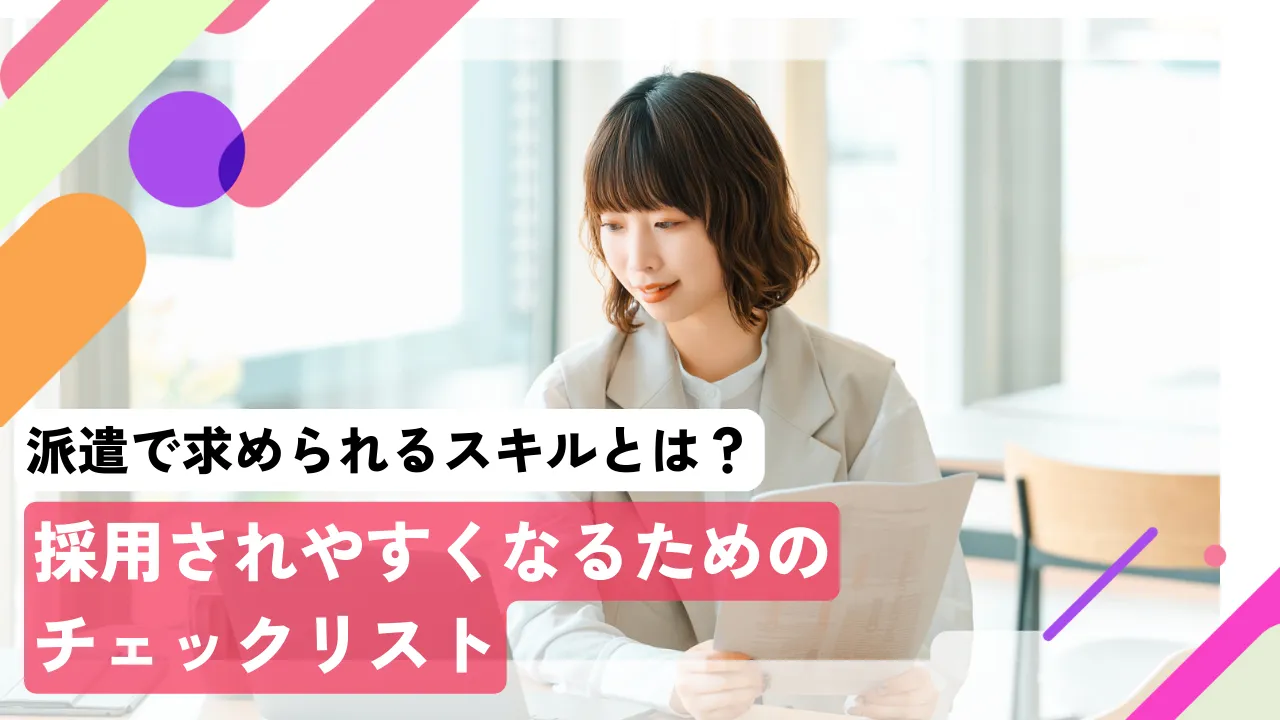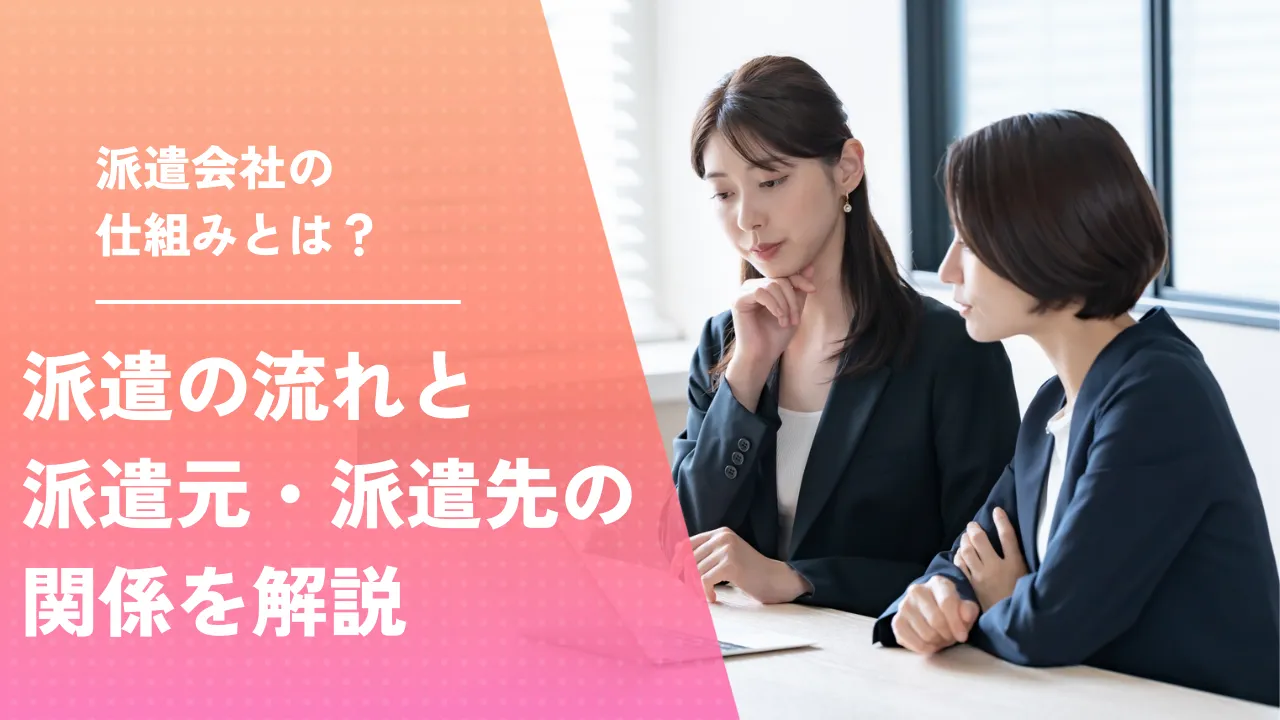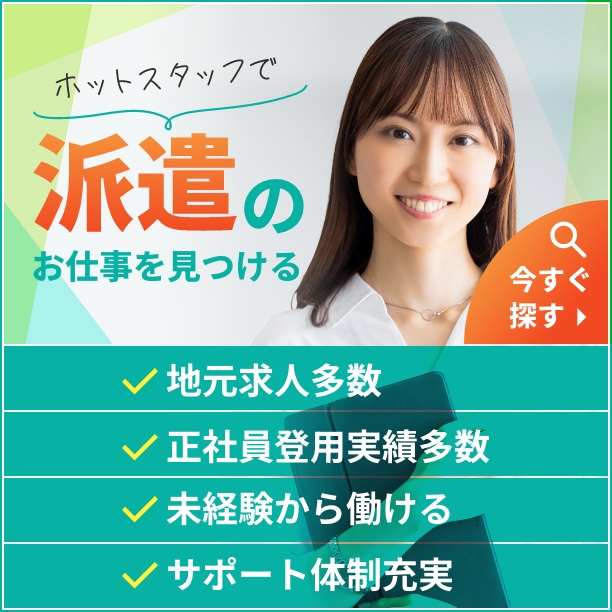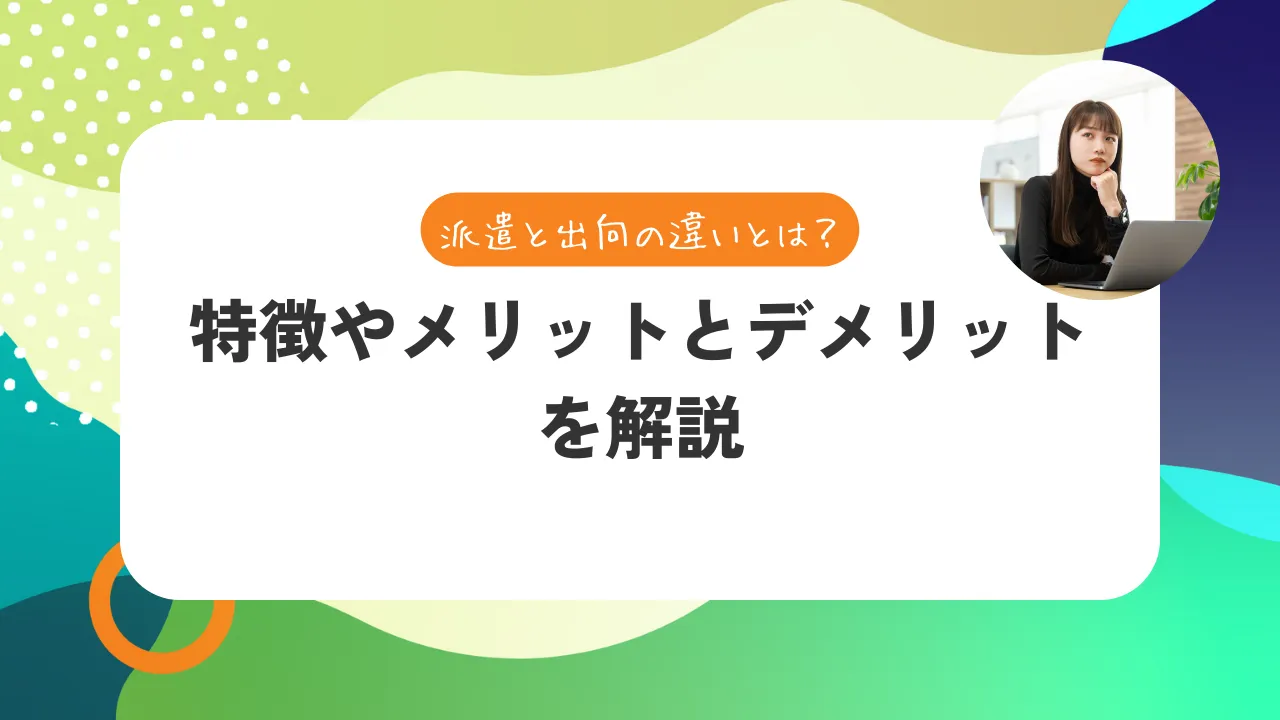「扶養内で働きたいけど、派遣でも大丈夫?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
派遣社員として働く場合でも扶養に入ることは可能ですが、税制上・社会保険上の扶養では、それぞれ異なる条件を満たす必要があります。
そこで本記事では、派遣社員が扶養内で働く際に知っておきたい条件や注意点を詳しく解説します。
税金や社会保険料の負担を抑えて、手取りをできるだけ多く残したい方は、ぜひ最後までお読みください。
扶養の種類

扶養には、“税制上の扶養”と“社会保険上の扶養”の2種類があります。
本題に入る前に、まずはこれらの概要を把握しておきましょう。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、一定の条件を満たす親族を扶養親族として申告し、扶養する側(扶養者)の課税対象となる所得から控除できる制度のことです。
これにより、扶養者の所得税や住民税の負担を減らせます。
扶養の対象(被扶養者)となるのは、配偶者や子ども、親など、生計をともにしている家族です。
税制上の扶養控除には、“扶養控除”や“配偶者控除”、“配偶者特別控除”があり、それぞれ対象となる親族や条件に違いがあります。
詳細は、以下の表をご覧ください。
【税制上の扶養で受けられる所得控除の種類】
| 所得控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 扶養控除 | 扶養者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合、一定額の所得控除が受けられる |
| 配偶者控除 | 扶養者に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合(年間合計所得金額が58万円以下)、一定額の所得控除が受けられる |
| 配偶者特別控除 | 配偶者に58万円を超える所得があり、配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者の所得金額に応じて段階的に所得控除が受けられる |
派遣社員が扶養内で勤務する場合、いわゆる“年収の壁”を超えない限りは税制上の扶養から外れることはなく、上記の所得控除を受けられます。
【参照元】
国税庁「No.1180 扶養控除」
国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
社会保険上の扶養
一方、社会保険上の扶養とは、扶養者が勤務する会社を通して被扶養者も社会保険に加入できる制度のことです。
社会保険上の扶養に入ると、被扶養者は保険料の支払いが免除されます。
ただし、被扶養者の年収が一定額を超えて扶養から外れると、社会保険への加入義務が生じ、保険料の支払いが発生します。
社会保険上の扶養から外れる年収の上限ラインも、年収の壁の一つです。
なお、税制上の扶養控除を受けている場合でも、社会保険上の扶養に入ることは可能です。
関連記事:派遣社員が社会保険に加入する条件とは?対象者や手続きの流れを解説
年収の壁とは

派遣社員が扶養内で働くうえで、税制上・社会保険上の扶養に共通する重要な条件の一つが、年収の壁とよばれる収入の目安です。
ご自身の年収によって扶養に入れるかどうかが決まり、また所得税や住民税、社会保険料の額も変わるため、扶養内で働きたい派遣社員の方は意識しなければなりません。
本項では、以下の6つの年収の壁について、それぞれ詳しく解説します。
【年収の壁】
- 106万円の壁
- 110万円の壁
- 123万円の壁
- 130万円の壁
- 160万円の壁
- 201万円の壁
106万円の壁
最初の106万円の壁は、社会保険への加入義務が生じるボーダーラインのことです。
この年収を超えると原則として扶養から外れるため、派遣会社を通して社会保険に加入し、保険料を毎月支払う必要があります。
ただし、以下の“社会保険の加入義務が生じる条件”のうち、一つでも該当しないものがある場合は、106万円の壁を超えても扶養に入りつづけることができます。
【社会保険への加入義務が生じる条件】
- 給与が8万8,000円以上
- 週の勤務時間が20時間以上
- 2か月以上働く予定がある
- 学生ではない
- 従業員数が51人以上
上記の要件をすべて満たしているかどうかが、社会保険の扶養適用の可否を判断するポイントです。
たとえば、ご自身が登録している派遣会社の従業員数が50人以下なのであれば、年収が106万円を超えても社会保険への加入義務は発生しません。
参照元:厚生労働省「社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について」
110万円の壁
次の110万円の壁とは、住民税の課税対象となる目安のことです。
令和7年度の税制改正に伴い、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に変更されたことで、課税対象となる所得が減額されました。
その結果、以前は100万円がボーダーラインだった住民税が発生する目安の額も、110万円に引き上げられています。
ただし、住民税の算出方法は自治体によって異なるため、年収が110万円に満たなくても課税対象になる場合があります。
住民税の算出方法や金額を確認したい場合は、ご自身の居住地の自治体に問い合わせてください。
参照元:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
123万円の壁
被扶養者の年収が123万円を超えると、扶養者は配偶者控除を受けられなくなります。
配偶者控除は、被扶養者の年間合計所得が58万円以下の場合に、扶養者の所得から一定額が控除され、税負担を軽減できる制度です。
給与所得控除の最低保障額が65万円であり、この額と58万円の合計が123万円になることから、配偶者控除を受けられるボーダーラインとなります。
一方で、仮に123万円の壁を超えて配偶者控除を受けられなくても、配偶者特別控除によって扶養者の税負担を抑えられる場合があります。
配偶者特別控除では、被扶養者の年間の合計所得に応じて、年収123万円から201万5,999円までは段階的に所得控除を受けることが可能です。
【参照元】
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)p4」
130万円の壁
130万円以上の年収がある場合、106万円の壁で扶養から外れなかった方でも、派遣会社を通して社会保険へ加入しなければなりません。
社会保険料の支払いが発生しますが、万が一のときの保障や老後の安定につながる大切な投資ともいえます。
なお、繁忙期の対応や人手不足を理由に勤務時間が延長され、一時的に年収が130万円を超えてしまうこともあるでしょう。
その場合、雇用元である派遣会社が「一時的な勤務時間の延長による年収超過であること」を証明すれば、2年を上限として扶養内に留まることが可能です。
【参照元】
厚生労働省「パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへp1」
厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&Ap4」
160万円の壁
160万円の壁は、先述した配偶者特別控除が段階的に減額され始める目安です。
年収123万円から201万5,999円までは配偶者特別控除が適用されますが、年収が160万円を超えると徐々に控除額が減っていきます。
160万円の壁にはもう一つの意味があり、それは所得税が非課税となる基準のことです。
令和7年の税制改正により、所得税がかからない年収の上限が、従来の103万円から160万円へと引き上げられました。
これは、税制改正で給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられ、基礎控除額も95万円に変更されたことにより、課税対象となる所得の基準が見直されたためです。
被扶養者の年収が160万円を超えると、所得税・住民税・社会保険料が発生することから、扶養者の手元に残る額は大幅に少なくなります。
201万円の壁
配偶者特別控除は、年収201万6,000円を超えると完全に対象外になります。
201万円の壁を超えた時点で、税制上の扶養と社会保険上の扶養から抜けることになるため、世帯全体の税金や社会保険料の負担が増加します。
派遣社員が扶養内で働くための条件

税制上・社会保険上の扶養にかかわらず、派遣社員が扶養内で勤務する際は、年収の壁以外の条件も満たす必要があります。
ここからは、年収の壁も含めて、扶養内で働くための条件を紹介します。
税制上の扶養に入るための条件
税制上の扶養に入ると、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除を受けられます。
各控除にはいくつかの条件が設けられており、これらをすべて満たす必要があるため、一つひとつ確認していきましょう。
【税制上の扶養で所得控除を受けるための条件】
| 所得控除の種類 | 条件 |
|---|---|
| 扶養控除 | ・被扶養者の年間合計所得が58万円以下(給与所得のみは123万円以下)であること ・配偶者以外の親族や里子(都道府県から養育を委託された児童)、または市町村長から養護を委託された老人であること ・扶養者と生計を一にしていること ・扶養者が年末調整を行った年の12月31日時点で16歳以上の親族であること |
| 配偶者控除 | ・扶養者の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと ・被扶養者の年間合計所得金額が58万円以下(給与所得のみは123万円以下)であること ・民法上の規定で配偶者と認められていること(内縁関係は対象外) ・扶養者と生計を一にしていること |
| 配偶者特別控除 | ・扶養者の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと ・被扶養者の年間合計所得金額が58万円超133万円以下であること ・民法上の規定で配偶者と認められていること(内縁関係は対象外) ・扶養者と生計を一にしていること ・配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと ・配偶者が源泉控除対象配偶者として申告されていないこと |
上記のいずれの控除を受ける場合にも、扶養者と生計を一にしていることが求められます。
これは必ずしも、扶養者と同居していることを意味するものではありません。
“生計を一にする”とは、 同じ家計で生活している状態のことです。
別居していても定期的な仕送りがあれば認められるため、親元を離れている学生や地方に住んでいる両親なども、“扶養者と生計を一にしている”と見なされます。
【参照元】
国税庁「No.1180 扶養控除」
国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)p4」
社会保険上の扶養に入るための条件
続いて、社会保険上の扶養に入るための条件を紹介します。
【社会保険上の扶養に入るための条件】
- 年収が130万円未満(60歳以上、または障がい者の場合は年収180万円未満)であること
- 配偶者(事実婚を含む)、または3親等内の親族であること
- 国内に居住していること
まず、130万円の壁を超えないことが社会保険上の扶養に入るうえで重要な条件です。
くわえて、扶養者の配偶者や3親等内の親族である必要があります。
社会保険上の扶養では、事実婚であっても配偶者として認められる点が税制上の扶養とは異なります。
ただし、配偶者の3親等内の親族や、事実上の婚姻関係にある配偶者の父母や子どもなどが被扶養者と認定されるためには、扶養者と同居していなければなりません。
年収の上限や、対象となる親族の範囲のほか、社会保険上の被扶養者は国内居住者に限定される点にも注意が必要です。
この要件は、令和2年4月に施行された健康保険法の一部改正によって新たに追加されました。
なお、社会保険上の扶養に関しては、税制上の扶養控除のような年齢の制限がありません。
関連記事:派遣社員は厚生年金に加入できる?国民年金との違いや加入条件を詳しく解説
【参照元】
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
日本年金機構「【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について」
派遣社員が扶養内で働く際の注意点
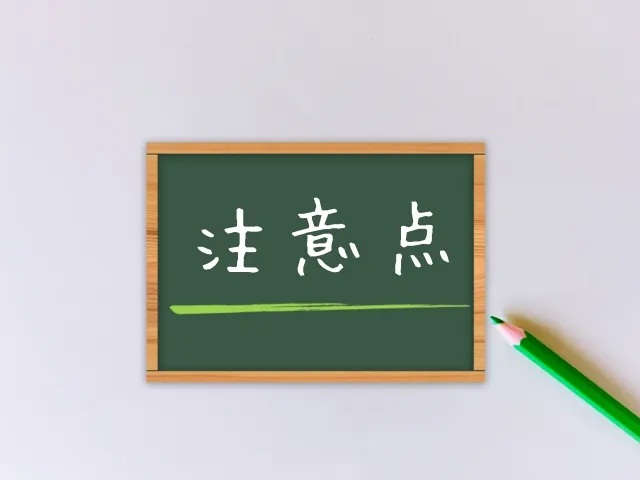
最後に、扶養内で派遣社員として働く際に押さえておきたい注意点を解説します。
以下の6点を意識して、扶養の範囲を超えないよう調整しながら、世帯収入をできるだけ多く手元に残しましょう。
【派遣社員が扶養内で働く際の注意点】
- 注意点①月収ではなく年収ベースで考える
- 注意点②残業時間を把握する
- 注意点③世帯年収を考慮する
- 注意点④扶養に関する手続きをきちんと行う
- 注意点⑤扶養内で働きたい意思を派遣会社に伝える
- 注意点⑥サポート体制が整っている派遣会社を選ぶ
注意点①月収ではなく年収ベースで考える
“年収の壁”という言葉があるように、扶養に入れるかどうかは年収で決まります。
派遣社員は、3か月から6か月程度の短期契約を結ぶこともあり、1年間に複数の更新や契約が発生するケースも珍しくありません。
その場合、月収だけでなく「年収はいくらになるか」をしっかり管理しておかないと、誤って年収の壁を超えてしまう可能性があります。
関連記事:派遣会社の選び方を解説!失敗しないための5つのチェックポイント
注意点②残業時間を把握する
派遣社員として扶養内で働く際は、残業時間をきちんと把握しておく必要があります。
派遣契約は契約書に記載された就業時間で働くのが一般的ですが、なかには残業ありの求人も存在します。
このような派遣先企業で働く場合、何度も残業が続くようであれば、年収が想定以上に増える可能性があるため注意しましょう。
扶養内で働く際には、実際の勤務時間数をきちんと把握したうえで、残業代を加えた年収を算出することが大切です。
注意点③世帯年収を考慮する
収入をできるだけ多く手元に残すためには、派遣の仕事で得た収入だけではなく、扶養者の年収も含めて、家計全体のバランスを見直す視点が求められます。
派遣社員として扶養内で働いたほうが得か、それとも扶養から外れて年収を増やしたほうが家計にプラスになるのかを計算することが重要です。
扶養内勤務が必ずしも家計に良い影響を与えるとは限らないことを踏まえて、「派遣でどの程度稼ぐのか」を、家族と相談しながら決めるとよいでしょう。
注意点④扶養に関する手続きをきちんと行う
扶養に入って控除を受ける際や、扶養から外れる際には、忘れずに手続きを行うことが大切です。
たとえば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象として扶養に入るには、年末調整あるいは確定申告の際に申請しなければなりません。
また、社会保険上の扶養に入る際は、扶養者が勤める会社に申請して担当者に手続きを進めてもらいます。
このような手続きを怠ると、控除が受けられなかったり、社会保険の扶養認定が遅れたりする可能性があります。
くわえて、扶養から外れる際の申告が遅れた場合は、税金や社会保険料をあとから支払うことになるため注意が必要です。
こうしたトラブルを避けるためにも、扶養の開始や終了があった場合は速やかに対応することが重要です。
注意点⑤扶養内で働きたい意思を派遣会社に伝える
「年収の壁をどうしても超えたくない」とお考えの方は、派遣会社の担当者にその旨をあらかじめ伝えておくのがおすすめです。
派遣会社によっては、登録時に希望の年収額を聞いたうえで、その範囲を超えないような求人を紹介してくれるところもあります。
このように派遣会社の担当者と連携することで、安心して扶養内勤務を続けられます。
注意点⑥サポート体制が整っている派遣会社を選ぶ
扶養内で派遣社員として働く際は、年収の希望を聞いてくれるだけでなく、気軽に相談できる体制が整っている派遣会社を選びましょう。
派遣会社の担当者と十分なコミュニケーションを取ることで、ご自身が希望する年収に達する前に、勤務時間やシフトを調整してくれます。
そのため、「いつの間にか扶養の範囲を超えてしまった」というトラブルを未然に防げるわけです。
たとえば、ホットスタッフでは、登録時にカウンセリング形式の面談を実施したうえで、就業開始後も専任の担当者がマンツーマンでサポートします。
「扶養内で働きたい」という要望にも柔軟に対応し、年収の壁を超えないような働き方を提案するため、収入を調整しながら働くことが可能です。
関連記事:派遣が初めての方必見!登録~就業開始の流れを徹底解説
派遣社員が扶養内で働くためには、年収の上限などの条件を満たす必要がある
扶養内で派遣社員として働く際は、税制上・社会保険上のいずれの扶養においても年収の壁を意識することが重要です。
税制上の扶養では、所得控除の適用が年収によって左右されます。
また、年収が130万円を超えると扶養から外れて、ご自身で社会保険に加入し、保険料を支払う義務が生じます。
扶養に入るための条件は年収だけではありません。
制度ごとに異なる基準があるため、事前にそれぞれの条件を確認しておくことが大切です。
扶養内で働くことを前提に、派遣登録を検討している方は、ホットスタッフにご相談ください。
専任の担当者が、一人ひとりに合ったお仕事を紹介しますので、扶養内勤務を希望する方でも安心して働けます。